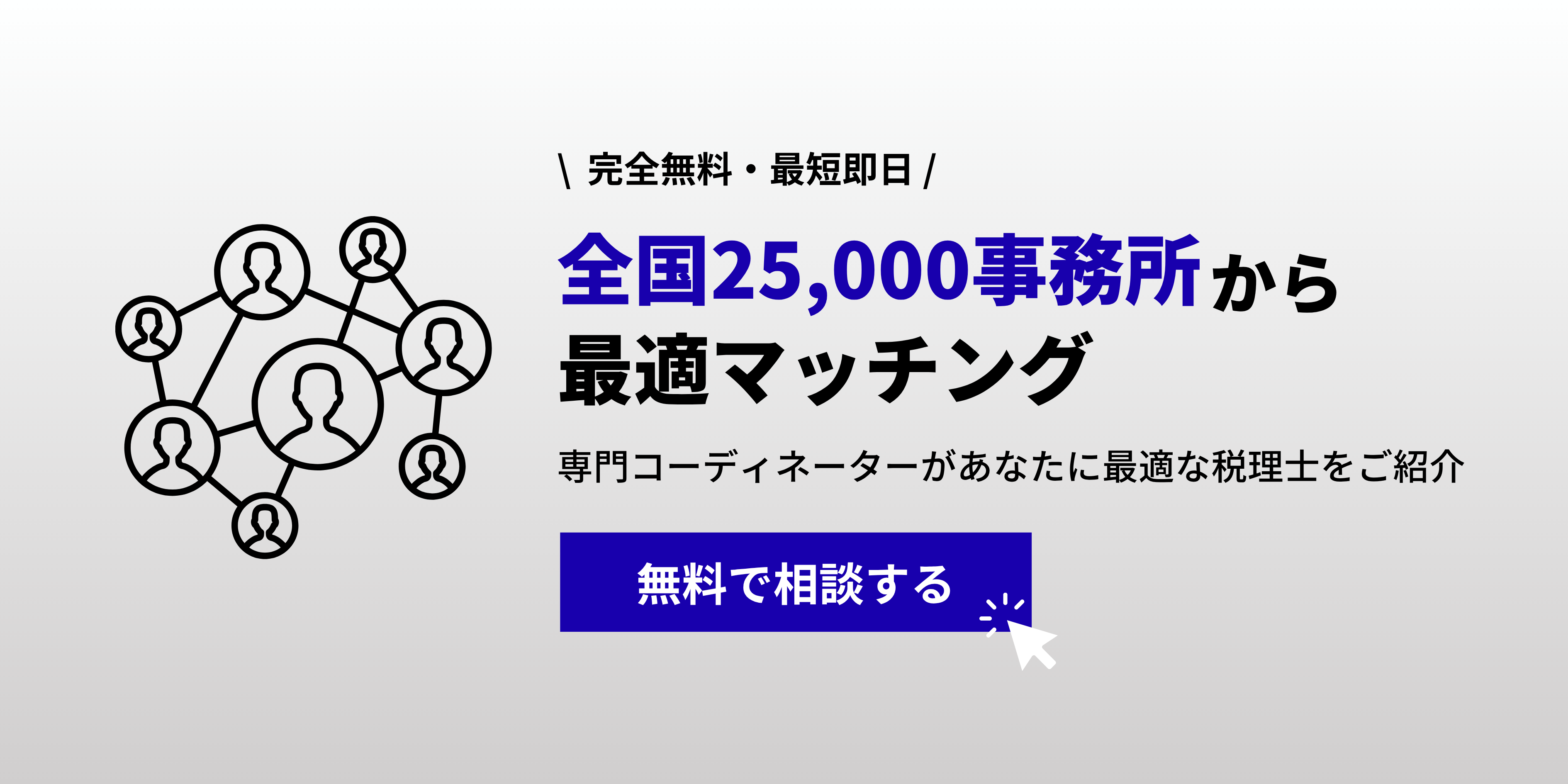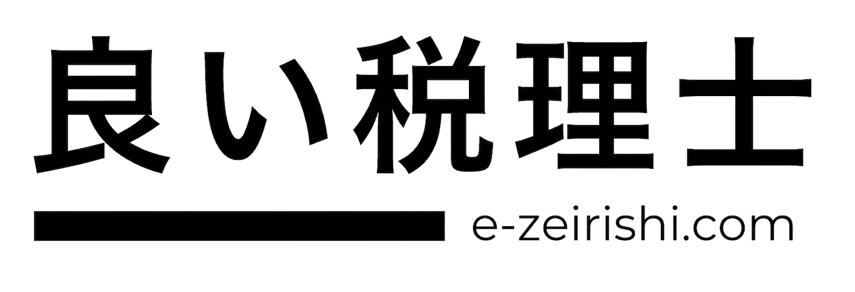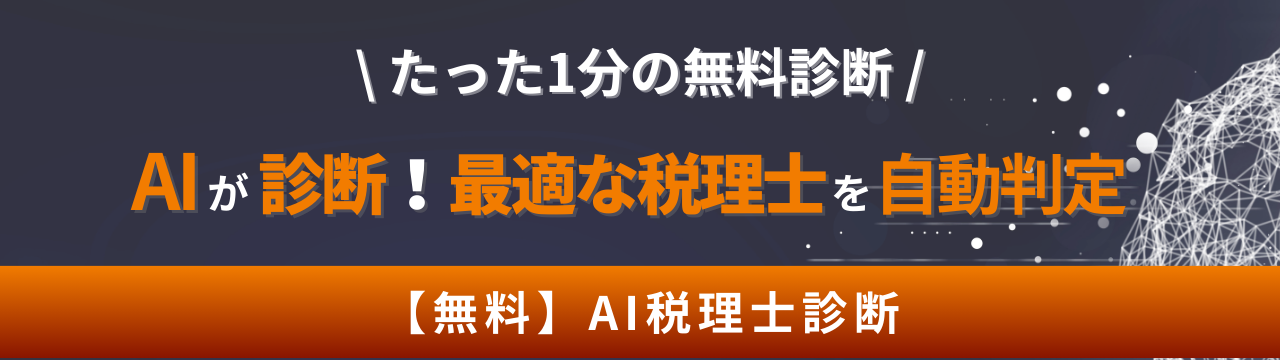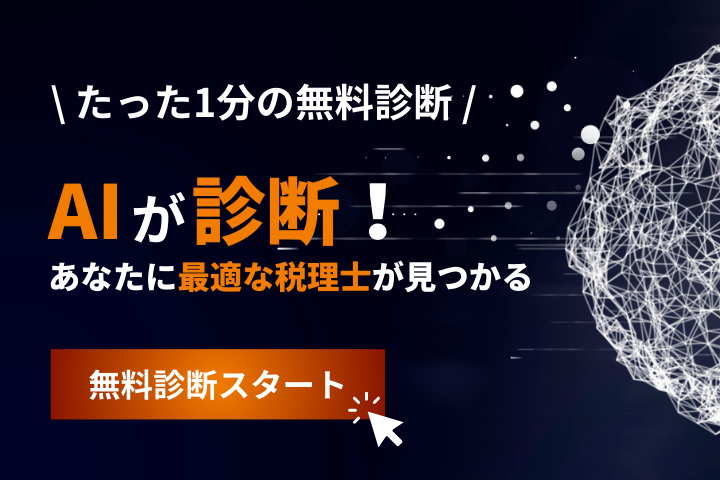税理士×大家×経営参謀。「自ら実践する」から語れるリアルな提案力

高井 興(たかい はじめ)|税理士法人タカイ会計 代表
1974年2月12日、名古屋市生まれ。
滝高等学校を卒業後、立教大学社会学部に進学し1997年に卒業。
卒業後はコーエーやコナミでゲームサウンドクリエイターとして活躍。
その後、第55回税理士試験に合格し、2006年に税理士法人タカイ会計を設立。
インタビュアー:本日はお時間をいただきありがとうございます。まず、高井さんが税理士を目指されたきっかけから教えていただけますか?
一言で言うと、「このままじゃダメだ」と思ったことがきっかけです。私は大学を卒業した後、ゲーム会社でサウンドクリエイターをしていました。担当は作曲。いわゆる“音楽を作る仕事”ですが、仕事内容はなかなかハードでした。
というのも、クリエイティブな仕事ってゴールがないんですよ。やればやるほどクオリティを追求したくなるし、でも業務としてやっているから納期もあるし、量もこなさなきゃいけない。当時の業界は今以上にブラックで、土日もなく深夜残業も当たり前。20代後半に差しかかったとき、「一生これを続けるのは無理だ」と限界を感じました。
インタビュアー:そこから、なぜ税理士という道に?
実は祖父が税理士だったんです。私が資格を目指した時点ではもう他界していたので、顧客を引き継ぐとかそういう話ではなかったんですけど、親から「税理士っていいらしいよ。資格があれば食っていけるし、独立もできる」とすすめられて。軽い感じのアドバイスだったんですけど、当時の自分にはそれが妙に響いたんです。
ゲーム業界にいると、転職も難しかったんですよ。私のような“サウンド専門職”が、一般企業に転職するのは至難の業です。だったら何か手に職をつけて、自分で独立するしかない。そう考えて、税理士という選択肢にたどり着きました。
インタビュアー:税理士についての知識はその時点であまりなかった?
まったくと言っていいほどなかったですね(笑)。「なんか資格っぽい」「独立できそう」くらいの感覚です。でも、音楽という“答えのない仕事”に疲れていた分、“答えのある仕事”に惹かれたのかもしれません。
インタビュアー:そこからどのように資格取得を進めていったんでしょうか?
一度会社を辞めて、町の小さな税理士事務所で働きながら勉強を始めました。さらに大学院にも通って、一部の科目免除を受けつつ、仕事と勉強を同時に進めていきました。勉強期間は約5年。20代後半から30代前半にかけて、ずっと勉強漬けでした。周りが遊んでいる中で、自分だけ先の見えない日々を過ごしていて、「自分の人生、これで本当に大丈夫かな」と不安になったこともあります。
でもあの時期があったからこそ、今の自分があると思っています。本当に、人生の大きな転機でした。
インタビュアー:資格を取得されたあとは、すぐに独立されたのでしょうか?
はい、ほぼすぐに独立しました。税理士になってから「中小企業を元気にしたい!」みたいな立派な理念があったかというと、正直なところ当時はそんな余裕もなかったです。とにかく「早く食えるようにならないとヤバい」という気持ちが強かったですね。すべては生活のため。家族を養うためでした。
資格取得に向けて大学院、実務、試験勉強を全部並行してやっていたのも、できるだけ最短距離で“稼げる税理士”になるためでした。だからこそ、資格を取った瞬間から「よし、もう独立しよう」と決めていました。
インタビュアー:それはすごい決断ですね。独立当初、不安はありませんでしたか?
ありましたよ、もちろん。資格は取れたけれど実務経験は5年しかなくて、基本的なことは一通りできたけど、実務的にはビビりながらやっていた部分も多かったです。
それに一番の不安は「お客さんが来るかどうか」。独立したてのころは、妻に「今日のご飯何にする?」って聞かれても「それより売上どうしたら上がると思う?」って、そんなことばかり話していたらしいです(笑)。今思うと病んでますよね。
インタビュアー:奥様も税理士をされているんですよね?
そうなんです。実は妻も同じタイミングで資格を取得していて、大学院で出会ったんです。なので、最初から二人で事務所を始めました。今では副代表として、私以上に内部の仕組みづくりやスタッフのマネジメントをしてくれています。僕は営業や会社の進むべき道、方向性を考える役割です。
インタビュアー:開業直後は、どのようにしてお客さんを獲得されたのですか?
あらゆる営業手法を試しました。本当に全部やりましたよ。Web集客、リスティング広告、SEO、電話営業、紹介会社への登録、飛び込み営業、異業種交流会、知り合いのつてをたどる……。中には、友達の親御さんに声をかけて嫌われたりもしました(笑)。いろいろ失敗しながら、少しずつ「こういう営業は嫌われるんだな」「これはうまくいくな」と学んでいった感じです。
インタビュアー:そこからどのように軌道に乗っていったのでしょう?
3年目ぐらいに急にお客さんが増えたんです。それ以降はほとんど紹介だけで増えていって、事務所としても安定してきました。
最初の頃は「資産税が得意です」「法人に強いです」なんて謳っていましたが、今思えば青かったなと。やっぱり税理士の実力って、どれだけ経験しているかで決まるんです。どれだけ勉強しても、現場で見てきた件数には敵わない。だから、最初から“できるフリ”をするより、とにかく経験を積むのが一番だと思っています。

インタビュアー:開業後、順調にお客さまが増えていったとのことですが、事務所としての方向性や強みが明確になってきたのは、どのあたりからだったのでしょうか?
きっかけになったのは、リーマンショックの直後ですね。当時は本当にたくさんの中小企業が苦しんでいました。資金繰りが回らない、銀行からお金を借りられない、返済のリスケも断られる。今では考えられないような状況でした。
そんな中、当時施行された「中小企業金融円滑化法(通称:亀井法案)」をきっかけに、事業再生や財務コンサルのニーズが一気に高まったんです。私自身も手探りで、財務改善の支援やモニタリング業務、再生計画の策定などを始めるようになりました。
インタビュアー:まさに「数字の伴走者」としての役割ですね。
そうですね。当時は“会計事務所”というより、むしろ“経営参謀”のような立ち位置でお付き合いするケースが増えました。金融機関の目線を意識して、決算書をどう整えるか、どう話をすれば融資が通りやすいか。そんなアドバイスをしているうちに、銀行から「ぜひ相談に乗ってほしい」と企業をご紹介いただくことが増えました。
「融資支援ができる税理士事務所」として少しずつ知られるようになったのも、この頃です。
インタビュアー:そうした経験が、今の事務所の基盤にもつながっているのでしょうか?
間違いなくつながっています。あのとき学んだのは、「財務の知識や数字の作り方一つで、企業の未来が変わる」ということ。たとえば、同じ利益でも勘定科目の使い方や表示の仕方で、金融機関の評価は大きく変わります。
うちは今でも、元金融機関出身のスタッフが在籍していて、決算書の“見せ方”にかなりこだわっています。お客様から「いい決算書を作ってくれたおかげで融資が通りました!」と言っていただくこともありまして。もちろん最終的に融資が下りるのはお客様の努力あってこそですが、そう言ってもらえるのはやっぱり嬉しいですね。
インタビュアー:まさに、経営者に寄り添う“伴走型の税理士”という印象です。
ありがとうございます。今でこそ「不動産専門税理士」としての発信をしていますが、その土台にはこうした“経営支援型の会計事務所”としての積み重ねがあります。
いきなり専門特化したわけではなく、泥臭くやってきたからこそ、今の強みがあるんです。
インタビュアー:現在は「不動産専門税理士」としても発信されていますが、そちらに注力するようになったきっかけは何だったのでしょうか?
大きな転機になったのは、やっぱりコロナですね。うちの顧問先にも飲食店が多くいたんですが、ある日突然、売上がゼロになるような現実を目の当たりにして、「事業って、こんなにあっさり止まるのか」と愕然としました。
会計事務所は比較的安定している業態ではあるんですが、とはいえ自分に万が一のことが起きたらどうなるんだろう、という漠然とした不安が芽生えたんです。そう考えると、何か“第二の柱”のようなものを持っておくべきだと強く思いました。
インタビュアー:その選択肢として不動産を選ばれた?
そうですね。ちょうどその頃、うちのお客さんに若手の不動産投資家の方が何人かいらっしゃって。そのうちのお一方から教えていただき、不動産賃貸業を始めました。最初はアパートを1棟買って、それから何棟か買い増して……と、気づけばそれなりの規模になってましたね。
インタビュアー:実際にご自身でも運用されてみて、どんな気づきがありましたか?
一番大きかったのは、「不動産税務って、こんなに癖があるのか」という発見ですね。これまでも不動産業のクライアントはいたんですが、やっぱりやってみないと分からない部分って多いんです。特に消費税まわりの処理はとても複雑で、知らないうちに間違えていることも多くあります。
実際、他の税理士さんが誤って処理していて、うちに移ってきたお客さんが過去に多く納めすぎていた、なんてケースもありました。それを見て、「あ、これは専門特化できるな」と確信しました。
インタビュアー:自ら大家業をやっている税理士というのは、確かにレアな存在ですね。
そうなんですよ。その希少性もあってか、オーナーさん向けの勉強会やセミナーに講師として呼ばれるようになりました。そういう場でお話しすると、毎回何社かお問い合わせをいただけるんです。
さらにX(旧Twitter)で発信を始めてからは、毎月1〜2件は新規のご相談が来るようになりました。正直、それまでWebマーケティングは全然うまくいってなかったんですよ。リスティングもSEOも空振り続きで。
でも「不動産専門税理士」という肩書きでXで発信し始めたら、それが初めて当たったんです。なので今は、Webからのお問い合わせはほとんど不動産関係ばかりですね。
インタビュアー:リアルとSNS、両輪で専門性が伝わっていったのですね。
はい。しかも私自身がプレイヤーでもあるので、数字の話だけじゃなくて「不動産投資そのもの」の話でも盛り上がれる。これはかなり強みになってると思います。よく「ここまで話せる税理士さん、なかなかいませんね」と言っていただけます。
インタビュアー:タカイ会計さんの特長として「顧客の乗り換えが多い一方で、離脱はほとんどない」という話を伺いました。それは本当にすごいことだと思います。
そう言っていただけると嬉しいですね。実際、今うちのクライアント数は300社を超えていますが、「うちが原因で離れた」というケースは開業以来で5社あるかないかくらいです。年間でいえば、1件あるかないかのレベルですね。
インタビュアー:驚異的な数字です……!なぜそんなにも離脱が少ないのでしょう?
要因はいくつかあると思うんですが、一番は「コミュニケーションの丁寧さ」かなと自分では思っています。うちの事務所には、他ではあまりやらないような“おせっかいルール”がたくさんあるんですよ。
たとえば、税金の納付書を郵送で送ったあとに、届いた頃を見計らってお電話する。「届いていますか? 〇月〇日が納期限なので、忘れずにご対応くださいね」と。正直、めちゃくちゃ手間です。でも、こういう一手間で「忘れてました!」というトラブルを防げるんですよね。
普通の税理士事務所ではやらないことかもしれませんが、うちは全スタッフで徹底してやっています。こういう細かい気配りを「事務所全体のルール」にしていることが、結果として顧客満足につながっているのかなと。
担当者によって差が出ないように、業務フローも仕組み化していますし、納付スケジュールや書類の送付も一元管理しています。つまり、「どのスタッフが担当でも安心」な状態をつくる努力をしているんです。
インタビュアー:その姿勢が「乗り換えてよかった」と思ってもらえる理由にもなっているのでしょうね。
そうだと信じています。もともと、うちのお客様の多くは「他の税理士事務所からの乗り換え」で来られた方なんです。なので、「比較対象がある中でうちを選んでいただけている」という意識は強く持っています。
インタビュアー:反対に、離脱したケースというのは……?
たまにありますよ。たとえば、スタッフの対応に明確な問題があったケースもありましたし、お客様との距離感が難しくて……というのも。でも、本当にごくわずかです。
逆に、こちらからお断りするケースもあります。スタッフへの配慮に欠けるような言動が続いた方とは、ご契約を見直させていただいたこともあります。スタッフを守るのも、代表である自分の大事な仕事なので。
インタビュアー:そのスタンス、とても共感します。
ありがとうございます。もちろん、厳しいお客様やクレームに近いご意見をくださる方もいます。でも、一定のラインを超えない限り、どんなタイプのお客様でもしっかり受け止める姿勢は持っています。
結局は、人と人のつながりなんですよね。だからこそ、機械的じゃなく、丁寧に、地道に。一つひとつの対応を“おせっかい”だと思われるくらいしっかりやる。それが、うちの強みだと思っています。

インタビュアー:現在の事務所体制についても教えてください。スタッフの人数や体制、特徴などがあればぜひ。
今は全部で18人です。うち税理士が4人、社員が7人、パートさんが7人という構成ですね。これまで人をどんどん増やす方向でやってきたというよりも、「この人数でいかに生産性を高めるか」に注力してきました。
たとえばコロナ以降は、事務所内の改革をかなり進めました。当時100の仕事量を18人でこなしていたとしたら、今は同じ人数で130程度まで処理できるようになってます。残業も大幅に減っていますし、効率化の成果は数字にも出てきていますね。
インタビュアー:具体的には、どのような効率化を進められてきたのでしょうか?
いろんなことをやってきましたが、一つ大きかったのはJDLという税務会計システムが提供しているAI OCRの活用です。たとえば通帳の記帳情報なども、紙を見ながら手入力するのではなく、スキャンしてデータとして読み込む。それが当たり前になってからは、パートさんの作業もずいぶん変わりましたね。
そしてもう一つ重要なのが、いわゆる「属人化の排除」です。
インタビュアー:属人化の排除、ですか?
はい。業務のブラックボックス化を徹底的に避ける、という方針です。お客様の担当はもちろん固定ですが、日々の処理や決算などの実務は「誰がやっても同じ結果になる」ことを目指して体制を整えています。
たとえば、今年はAさんが決算を組んだけれども、来年はBさんが担当する。そういう循環を意図的に作っていて、情報やノウハウも一元化して管理しています。人に依存しない仕組みにしておくことで、人が入れ替わってもサービスの質を落とさずに回せる。これは、これから先さらに規模を拡大していく上でも、不可欠な考え方だと思っています。
インタビュアー:その先には、事務所としての「自走化」も視野に入れていると?
まさに、そこですね。私は今51歳ですが、あと20年このままリーダーでいるつもりはありません。事務所を継いでいってもらうには、“継ぎたくなるような組織”を作ることが大切です。そのためには、ルール・仕組み・文化すべてを言語化・可視化して、誰にでも運営可能な状態にしなければいけない。
私ひとりが全部を背負ってやってしまうと、それは属人化の最たるものになってしまうので、今は副代表である妻が内部体制の構築を主導しています。彼女は本当にそういった仕組み作りが得意で、私一人ではここまで整えられなかったと思います。
インタビュアー:まさに、組織で強くなる事務所ですね。
ありがたいことに、うちのパートさんも含めて皆さん優秀で、入力だけしかできないという方はもういません。そういうスタッフと、共通の仕組みの中で動ける体制を作っていく。地味なようで、これが一番の土台になります。
そしてこの土台があるからこそ、今後どれだけ規模が大きくなっても対応できる――そんな事務所に育てていきたいと思っています。
インタビュアー:今後、さらに注力していきたい分野があれば教えてください。
今後は「資産税」、とくに相続税の分野をもっと伸ばしていきたいと考えています。というのも、うちの社内にはすでに資産税チームがあり、難解な税務対応やイレギュラー案件にも対応できる体制が整っているんです。
加えて、このチームには元国税職員の税理士が在籍しています。50代中盤で、現役時代には資産課税部門の統括官――つまり、資産税のトップポジションを務めていた方です。実務も理論も、国税の内部事情に詳しく、非常に心強い存在ですね。
インタビュアー:その体制であれば、どんな相続案件でも安心して任せられそうですね。
はい、そう思います。現状でも相続のご相談は一定数いただいていますが、まだまだ潜在ニーズはあると感じています。ですので今は、司法書士さんなど他士業の方々と連携して、相続分野での新規顧客獲得にも力を入れているところです。
インタビュアー:不動産、財務コンサル、相続……すでにかなり幅広い対応が可能な事務所という印象を受けます。
そうですね。でも私たちのスタンスは一貫していて、「数字を通じて経営に貢献すること」です。それが融資支援であれ、不動産税務であれ、相続支援であれ、お客様の未来がより良くなるように数字を整えていく。それが我々の役割だと思っています。
インタビュアー:まさに“転ばぬ先の杖”ですね。
まさにそうです。うちはお客様に対して「おせっかい焼きすぎ」と思われるくらいがちょうどいいと考えています。だからこそ、うちを選んでくれる方が増えているのかなと。
それに最近は、若い起業家のお客様も増えていて。20代で会社を立ち上げた方なんかから「どうしたら人を雇えるようになりますか?」「これってリスク高いですかね?」なんて相談されると、ついつい“親戚のおじちゃん”的に話し込んでしまうんですよ(笑)。
自分自身がゼロから立ち上げて、スタッフも抱えて、色々苦労してきたからこそ、リアルな話ができるんですよね。年商いくらの時に何を考えていたか、人間関係で何に悩んだか……。そういう話が“リアルに語れる税理士”って、実は意外と少ないと思うんです。
インタビュアー:では最後に、これから税理士を探している方や、乗り換えを考えている方にメッセージをお願いします。
はい。うちは「乗り換え」に関しては本当に慣れてます。どんなタイミングでも、たとえ決算直前でも、うまく引き継ぐ方法を熟知しています。気になることがあれば、まずは気軽にご相談いただけたらと思います。
そして改めてになりますが、私たちは“おせっかいな税理士事務所”です。転ばぬ先の杖として、先回りしてリスクを潰す。そこに本気で取り組んでいるからこそ、安心して任せていただけるのではと思っています。
もし「今の税理士との関係、ちょっと気になるな…」と思っている方がいれば、ぜひ一度お話してみてください。

税理士法人タカイ会計のHPは こちら