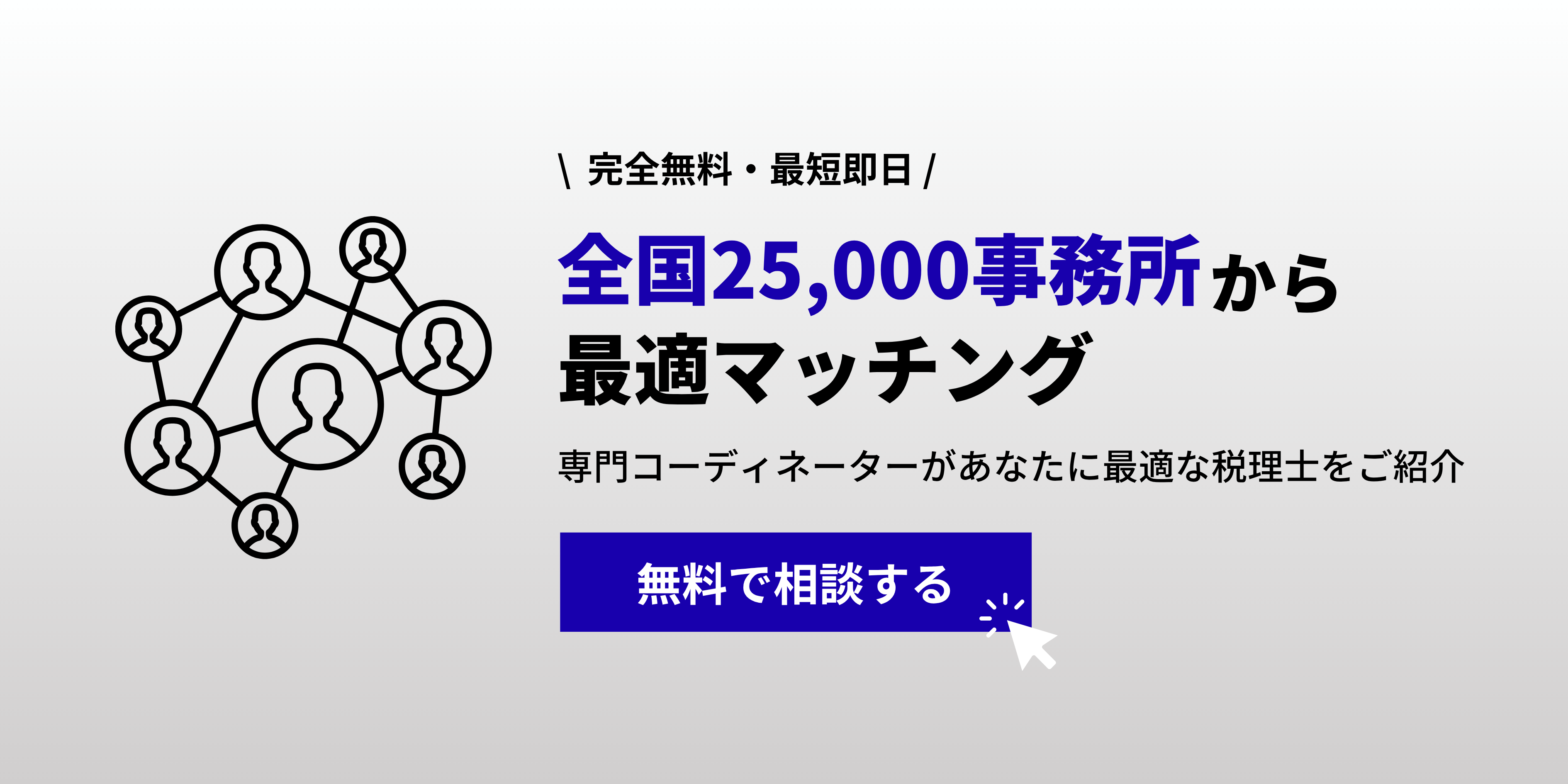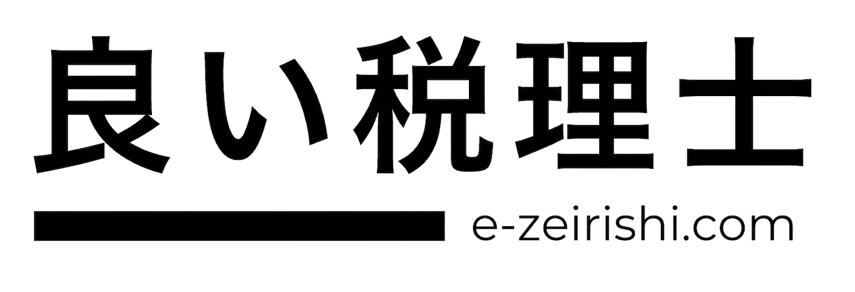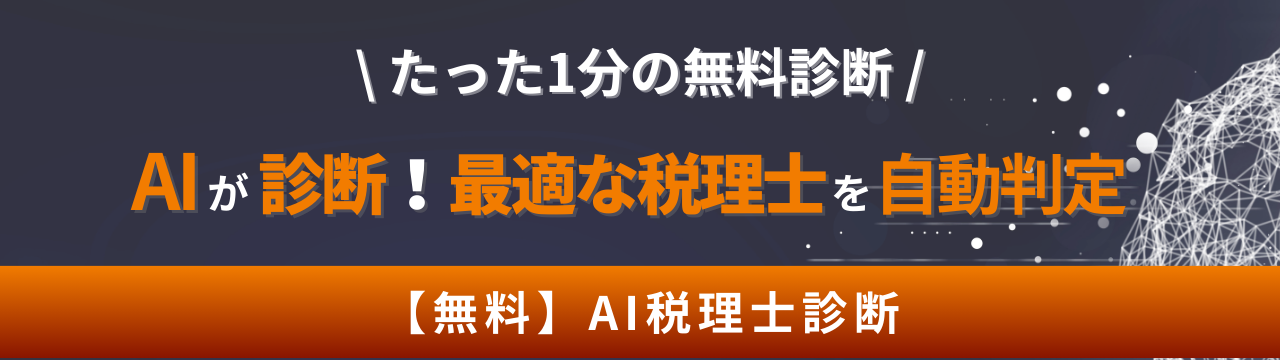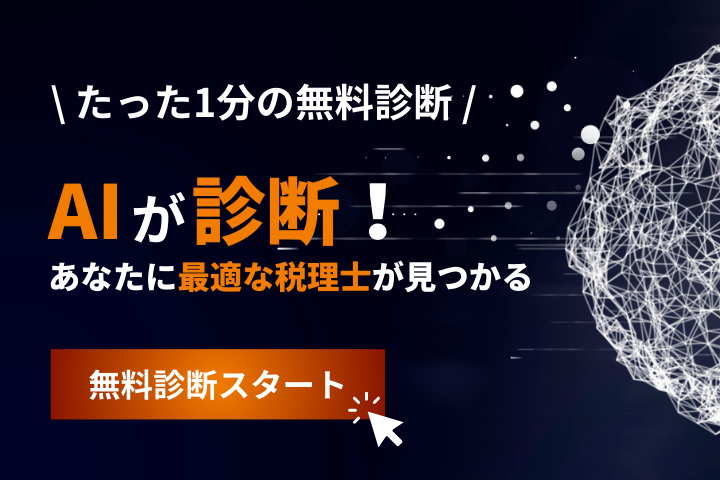父のリストラが導いた税理士の道。国税組織で最速MVP→適応障害→独立で見つけた自分の生き方
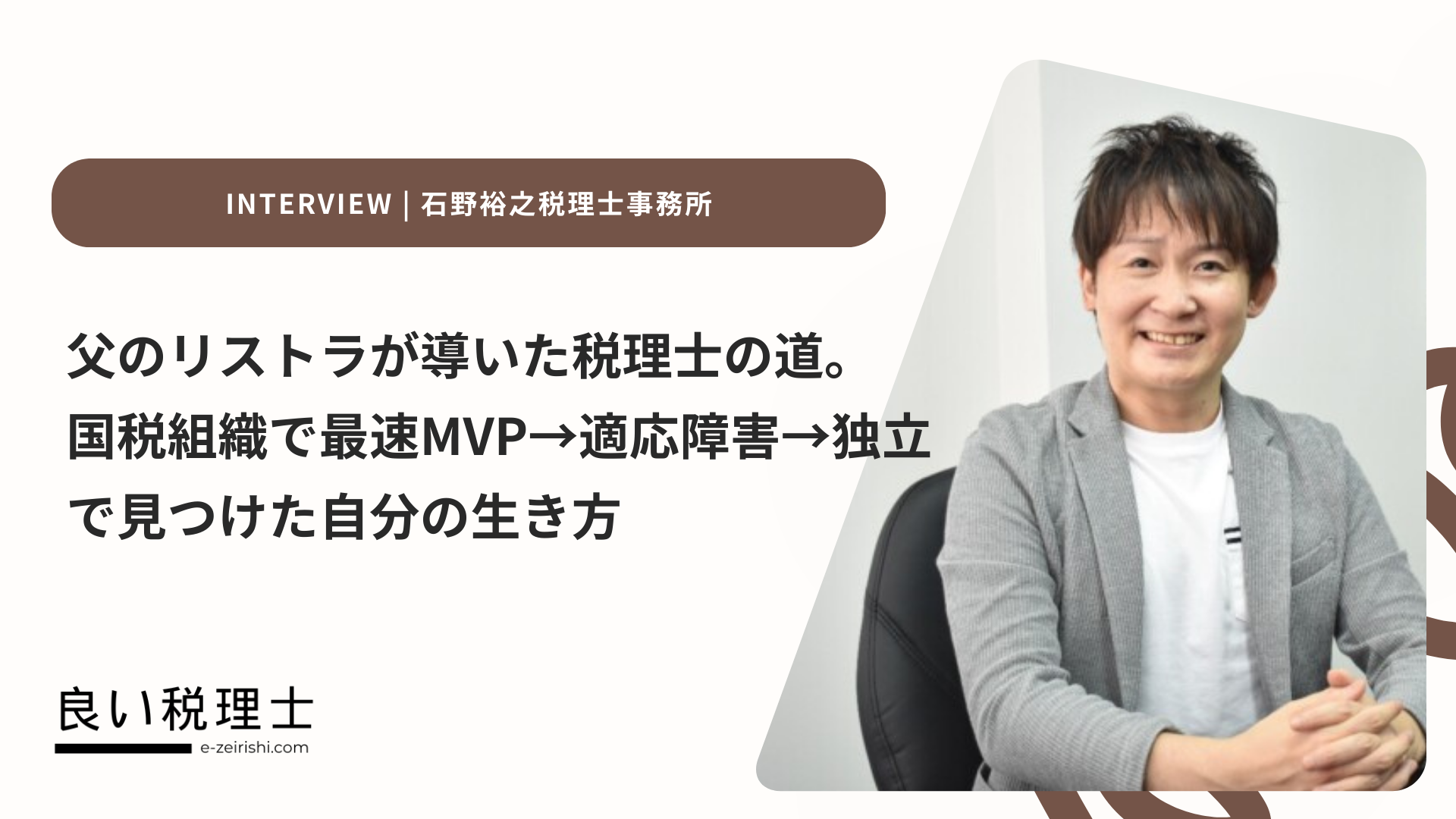
石野 裕之:石野裕之税理士事務所 所長税理士
1982年生まれ。兵庫県三田市出身。同志社大学法学部法律学科卒業。同年、関東信越国税局に入局。入局2年目に自身が手掛けた一般税務調査事案が優良事績として国税局長より表彰された実績や、法人調査にて、税務署長より優良賞を表彰された実績がある。
医療特化型税理士法人勤務、ベンチャー企業の経理主任を経て、2020年独立開業。税務調査対応、個人事業主の税務、クラウド会計やITツールを活用したバックオフィスの効率化等を得意としている。
――本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。石野さんは国税局にお勤めされた後、税理士として独立されていますが、まず税理士を目指されたきっかけから教えていただけますか?
税理士を意識するようになったのは、大学2年生の頃の出来事がきっかけです。当時、父が上場アパレル企業に勤めていたのですが、リストラにあいました。仕事一筋だった父は資格も持っておらず、再就職に大変苦労する姿を目の当たりにしました。そのとき「自分は特別、喋りが上手いわけでも世渡り上手でもない。組織にどっぷり依存するのは危険だ。何か目に見える武器を持たなければならない」と強く感じたのです。
そこから「手に職をつけなければ」という意識が芽生えました。大学時代は遊んでばかりでしたが、座学には自信があり、簿記2級や宅建などの資格を遊びの合間に取得しました。
大学3回生になると、成り行きで行政法ゼミに入りました。いざゼミに入ってみると、ほとんどの同級生が公務員志望。私は「公務員=安定、ぬるま湯」というイメージを持っていて、正直あまり格好良いとは感じていませんでした(公務員を目指されている方には申し訳ありません)。ただ、その中でも国税専門官は特殊で、どこか「格好良い存在」に見えました。マルサという部隊を擁し、専門的な知識や技術を武器に『社会悪』と戦う、そんなアクティブな公務員像に強く惹かれたのです。
就職活動を終えた後、国税を含む国家公務員試験の勉強を始めました。毎日13時間以上、自習室に籠もって集中し、大学受験時のセンター試験や宅建・行政書士試験で培った知識も活かせたことで、およそ3か月という短期間で国税専門官試験と国家公務員試験の両方に合格できました。
当時の国税専門官試験は、受験者数が約2万人に対して最終合格者が1,000人ほど。その中で合格できたのは、過去の蓄積と、当時の必死の努力の成果だったと思います。
――国税局では、最初から出世コースを歩まれていたのでしょうか。
絶対に出世してやる。大学受験も公務員試験も現役合格を果たし、「自分はエリートの部類だ」、そんな若気の至りもあって、自信満々で出世コースに乗ろうとしていました。
ところが、最初につまずいたのが、希望していた法人課税部門ではなく、個人課税部門に配属されたことです。国税組織は「法人課税部門」「個人課税部門」「資産課税部門」「徴収部門」の4系統に分かれており、最初の配属が「背番号」のように固定され、その後のキャリアを大きく左右します。他系統に異動するのは稀で、事実上その系統でのキャリアが続いていきます。
当時の私は「法人課税こそ国税の花形部門で格好良い」と信じ込んでいたので、個人課税部門への配属を告げられたときには大きなショックを受けました。落胆のあまり、担当教授に「納得できません。なぜ私は法人課税部門ではないのですか!」と直訴・嘆願したほどです。ちなみに今の私が当時に戻れるなら、税理士としての市場価値が高く、富裕層が相手となる資産課税部門を第一希望にするでしょう(笑)。
とはいえ、個人課税部門での経験は非常に有意義でした。個人事業主の税務調査や確定申告の相談対応が中心で、特に申告期は「お祭り」と呼ばれるほどの修羅場です。入局1年目には、関東信越国税局でも「3K」と言われる川口税務署に配属され、確定申告会場では怒号が飛び交う中、立ちっぱなしで1人あたり6人ほどの納税者の申告書作成を補助するという、まさにカオスな現場を経験しました。
そんな苛烈な環境の中でも「ありがとう」と感謝してくださる納税者も多く、公務員バッシングが盛んだった時代に、心が救われる瞬間を何度も味わえたことは大きな財産です。
――国税での業務はいかがでしたか?特に印象に残っている経験があれば教えてください。
2年目に大きな転機がありました。「優良事績発表会」という、困難な事案を解決したり、新しい調査手法を開発したりした職員が表彰される場に呼ばれ、いわばMVPのような賞をいただいたのです。
表彰された案件の多くは、あらかじめ「重要資料せん」と呼ばれる、脱税が見込まれる情報をもとに成果を出した事案でした。また、そんな中で、私が表彰された案件だけは、そうした情報が全くない状態からのスタートでした。別件調査の際に、数字の規則や配列に違和感のある領収書を見つけ、上司である統括官に「この発行者を調べたい」と申し出たのです。たまたまその事業主が統括官の選定した調査候補に挙がっており、臨場の機会を得ることができました。
調査先でPC内のデータを確認したところ、初日の午前中に脱税を発見することができました。統括官から「お前すげえな!」と言われた時の嬉しさは、今でも鮮明に覚えています。
ただ、2年目のひよっこ新人が「ひとつの頂点」を覗いてしまったことで、気持ちが冷めてしまった側面もありました。調査で成果を出せば称賛される一方、年度が替われば成績はリセットされ、またゼロからの繰り返し。成果が出なければ上司に叱責される。そんな終わりのないサイクルに、「この先ずっとこれを続けていくのか」と、自分の人生そのものに疑問を抱くようになったのです。
さらに調査の現場では、非違や脱税を見つけると、どこか嬉しくなってしまう自分がいました。本来であれば、帳簿をきちんと付け、正しく申告している真面目な事業者こそ評価・賞賛されるべきです。ところが現実には、上司に叱られないために粗探しをしてしまう。そんな自分の心理に、次第に強い違和感を覚えるようになったのです。
――調査官として優秀だったからこその悩みですね。
当時は説明や説得といったコミュニケーションが得意ではなく、先輩や上司に頼りきりでしたので、「優秀」とまでは言えません。ただ、不正を察知する嗅覚や、一度見た領収書を瞬時に思い出す“瞬間記憶力”については、周囲よりも抜きんでているという自信と自負がありました。(SNSでも「これは誰の裏アカか」を察してしまう特定力で証明してみせています笑。)
そして4年目、また大きな転機が訪れました。税務署版ミニ料調と呼ばれ、厳しい調査をする特別調査班に配属されたのですが、一緒に組んだ先輩の調査のスタイルが自分と全く合わなかったのです。私の調査手法はいわゆる「一点突破型」で、ここだと感じた部分を集中して攻め、外れたらすぐ諦めてしまうタイプでした。(諦めが早過ぎるとよく怒られました。)
一方、先輩のやり方は、(不正が見込まれない)どんな案件であっても「上司からの調査指示を受けた以上、非違を見つけられないのは我々の責任だ」という信念のもと、調査先に嫌われようが罵声を浴びようが反面調査を行い、あらゆるところを徹底的に隙間なく調べ上げる資料調査課伝統の「ローラー型」のスタイルでした。
私はその厳しいやり方についていけず、詰めの甘さを理由に叱責されることが増えました。銀行調査を含む反面調査のスケジュールもぎっしり詰め込まれ、次第に体調を崩していきました。ご飯が喉を通らず、朝は憂鬱な気分で目覚め、吐き気や下痢に悩まされる日々。気分は塞ぎ、改善の兆しも見えず、「このままでは壊れてしまうのでは」と不安を抱え、同僚に打ち明けて相談しました。
勇気を振り絞って上司や副署長に症状を伝えたところ、副署長の勧めでメンタルクリニックを受診し、「適応障害」と診断されました。
――適応障害という大変な体験をされたんですね。その時期はどのような心境でしたか?
当時、エリート意識が強かった私にとって、大きな挫折でした。優良事績に選ばれたことで「俺はできる」と天狗になっていた面もあり、3年目には筆頭統括官に嫌われ、国税局(いわゆる“本店”)に行けず、地方署に転勤し、厳しい調査に耐えきれずにメンタルを壊してしまいました。
さらに諸先輩方からは「逃げるな、これからも逃げ癖がつくぞ」「命令されたことは全うすべきだ」と後ろ指を刺されました。人事配置で決まったペアの解消を申し出ること自体が異例であり、しかもその先輩は調査力に定評のある方だったため、噂は周辺署にも広がり、私のいない酒席でさまざまなご指摘があったとも聞きました。肩身が狭く、辛い日々でした。ただ、その先輩自身は酒の席でも一切私を悪く言わなかったと同僚から伝え聞き、その姿勢には今でも敬意を感じています。2009年、入職から4年目の出来事でした。
適応障害を経験したことで、自分の中に根付いていたエリート意識は崩れ、「別の道を探そう」と人生を考え直すきっかけになりました。本当にやりたいことは何なのかを見つめ直す時間となり、結果的に大きな転機になったのです。
税理士になった今、あの先輩と調査の場で再び対峙し、スタンスの違いを自分なりに証明したい思いもありました。しかし、風の噂でその先輩が退職されたと聞き、残念さや寂しさ、そして心残りのような感情が入り混じっています。
――その体験が、税理士としての独立への決意を固めることにつながったのでしょうか?
そうですね。国税に13年間勤めた後、2018年に退職しました。閉鎖的な大組織の中で人生を終えることにモヤモヤ感があり、「俺はこんなところで終わる人間じゃない」というプライドもありました。もっと自分の知識や技能を活かせる場、アピールできる場所があるはずだ——そんな思いに突き動かされました。どちらかといえば、やり直したいという“負の感情”も大きな馬力になったと思います。
国税時代に培った調査スキルや税務知識は、税理士として活動する上で大きな武器になると考えました。特に税務調査については、調査官の立場を知っているからこそ、調査を受ける側の不安や悩みを和らげられる。調査官がどこを見るのか、どういう準備をすればよいのかは、元調査官だからこそ具体的にアドバイスできる部分です。
――国税を退職された後の流れを教えてください。
当時はまだ税理士界隈のSNSの存在すら知らず、情報も限られていたため、独立という発想は全くなく、まずは税理士法人に勤めました。医療特化の税理士法人だったのですが、それまでの国税時代の環境とは全く異なり、大きなカルチャーショックを受けました。
国税ではインターネットを使うにも申請が必要でしたが、その事務所ではフリーアドレス制で、パソコンとセカンドモニターが完備され、Dropboxなどのクラウドストレージも当たり前。職員にはiPhoneが支給され、Chatworkで会話や情報共有、サイボウズでスケジュール管理。会計事務所・税理士法人の中でも相当先進的な環境でした。
IT化が進んでいたのは良かったのですが、売上数十億の医療法人を任されて、正直怖かったです。法人税の経験は国税時代にもありましたが、いきなり大きな医療法人を担当するのは緊張しました。
しかも、外部委託の先生と共同で進めることも多く、各自が個人事業主の集まりのような雰囲気で、気軽に相談できる相手も少なかったです。私は普段から臆病というわけではありませんが、初めて経験する仕事に直面すると心配性で慎重になる性向が強く出てしまい、分からないことだらけでびくびくしていました。力不足を痛感し、「給料の対価に見合った仕事ができていない」と弱気になってしまい、自ら採用してくださった方に相談して給料を下げてもらいました。
そんな時に、東京青税で井ノ上陽一先生の研修を受ける機会があったんです。そこで「ひとり税理士」という働き方に衝撃を受けました。
――どのような内容だったのでしょうか?
井ノ上先生のプロフィールがとても印象的でした。「こういう仕事は受けたくない」「こういうことは苦手です」と、できないことも正直に書いてある。さらに趣味もオタク気質で、ゲームやアニメといったマニアックで個性的な要素まで自己紹介に盛り込まれていたんです。
自分の経歴や趣味、性格、ダメなところ、やりたくないことまで、かなり開けっぴろげに自己開示している。そんなHPを見て、「これは好き嫌いがはっきり分かれるけれど、自分にマッチするお客さんだけが残る仕組みになっている」と感じました。
旧態依然とした慣習の残る会計業界、特に競争が激しい東京では、肩書きや経歴、耳障りの良い理念など「外見」を取り繕う傾向が強いと感じていました。そんな中で、ここまで徹底した自己開示をしているのは異端であり、「こんな自己主張をしている先生、初めて見た」と衝撃を受けました。これなら自分と相性の良いお客さんだけが来るし、自然にフィルタリングもできる。そんな働き方があるのかと、まさに目から鱗でした。
自分のスキルややりたいことを改めて自己分析・棚卸しました。私はもともと個人課税部門出身で、お客さんと対話しながら仲良くなったり、窓口で税務相談に応じたり、教えたりするのが好きでした。当時勤めていた税理士法人では、周囲に追いつくのに2年はかかりそうだと感じていました。
だからこそ、「自分の国税での経験である個人と法人の調査対応、スモールビジネスの税務知識、現場実務経験、対行政実務経験などを活かせば、違うやり方で勝負できるのではないか」と考えるようになったのです。
――そこから開業までは早かったのですか?
大変お世話になり、非常に貴重な経験もさせていただいたのですが、半年で退職しました。ただ、いきなり独立開業したわけではなく、まずは開業税理士として登録をしつつ、たまたまご縁のあった勢いのあるベンチャー企業で経理主任を務めることになりました。いわゆる「副業開業」という形でのスタートでした。
そこで弥生会計をみっちり触り、記帳入力や給与計算スタッフの指導・教育を経験しました。さらに、ベンチャー企業ならではのスピード感や戦略、ブランディングの手法に加え、現場でしか見えない泥臭さにも触れる機会もありました。そうした現場のリアルを間近で学べたのは非常に貴重な経験になりました。
成果を出せば自由な働き方が許される環境でもありました。そんな中で、音声配信アプリVoicyで「チャラいパーマ税理士」として活動されていた大河内薫先生を知り、オンラインサロンに入会。実際にお会いした際に「Twitter(現X)をやった方がいいですよ」とアドバイスをいただき、SNSを始めるきっかけになりました。
当時はまだ税理士YouTuberが少なく、私も知り合いの税理士さんのYouTubeに出演しました。批判も多く寄せられましたが、それ以上に大きな反響がありました。Xを通じて交流の幅も広がり、さまざまな人とつながっていきました。
漫画家さんや芸能関係のクリエイターさんをメインの顧客にしている先生方と知り合えたことは、大きな財産になっています。
1年ほど活動を続ける中で、Xを通じたご縁から、知り合いの税理士さんに調査対応を依頼される機会があり、それが後に私のVIPクライアント様となりました。また、資料調査課の主査による乱暴な調査に対して、調査立会いに同行する機会をいただけたり、思いがけない形で経験やつながりが広がっていきました。
日本政策金融公庫の借入審査も無事に通過し、「これならなんとかやっていけそうだ。もしダメでも、税理士資格を担保に勤務税理士に戻ればいい」と、完全独立へと踏み出しました。
――青税のセミナーを受けてから開業まで、かなりの爆速ですね。
そうですね。いろいろな経験があったおかげで、マーケティングなどもスムーズに進められました。国税での経験、税理士法人での経験、ベンチャー企業での経験、それぞれが今の仕事に活きていると感じています。
――現在はどのようなクライアントさんを中心に対応されているのですか?
メインはクリエイター系の方々です。特に漫画家さんが多く、ほかにも芸能関係のクリエイターさんや、建設業、美容室、IT企業、学習塾など、幅広い業種の方とお付き合いがあります。現在の関与先は30社ほどで、地域に限定せず全国対応しています。
漫画家さんが多い理由としては、まず皆さん基本的にITリテラシーが高いという点があります。Discordでのやりとりや、ゲームのチャット機能など、デジタルコミュニケーションに慣れていらっしゃるので、業務も非常にスムーズです。
また、漫画家さんは地頭がいい方が多い印象です。ストーリー構成力やキャラクターの描写って、ただ絵が描けるだけでは成立しません。編集さんのサポートもありますが、それを活かす土台となる知性や洞察力がないとできない仕事だと感じます。
――確かに、クリエイティブな仕事には高い思考力が求められますね。そうした顧客層との関係で、石野さんが重視していることはありますか?
私自身、開業当初は「ひとり税理士」スタイルに憧れて、すべてを自分一人で完結させようとしていました。
クラウド会計やZoomなどのWeb会議ツールをはじめ、ITツールや文明の利器は最大限活用するようにしています。効率的かつ高品質なサービスを提供することが、双方にとって一番良いと考えているからです。
人と話すのは好きですが、訪問対応などに時間を取られるのはなるべく避けたかったんです。幸い、クリエイターの方々はその点に理解があり、むしろ「顔出しはNGでオンラインの方が都合が良い」という方も多く、相性がよかったですね。
――理想的なマッチングだったわけですね。
はい、ですがもちろん失敗もありました。
前任の先生が体調を崩されたこともあり、義理で引き受けたあるお客様は、売上規模も従業員数も大きな企業でした。ところが、記帳は非常に特殊でデータ量も多く、私が普段使っているツール等の導入も諸事情により、断られてしまいました。
しかも、その方は非常に頭の回転が速く、1分1秒を惜しむタイプで、前任の先生との長年の信頼関係があったからこそ成り立っていたような案件でした。コミュニケーションの取り方も独特で、正直、死ぬほど苦労しました。
この経験で強く学んだのは、「この仕事は受けてはいけない」という判断基準の大切さです。
自分のキャパや処理能力を超える案件を無理に引き受けると、最終的にはお客様にも迷惑がかかってしまいます。どれだけ義理があっても、「紹介を断る勇気」も必要なんだと学びました。
――今は、開業の醍醐味でもある「選択権」を活かしているわけですね。
そうですね。あの失敗があったからこそ、今のスタンスがあると思います。
やはり、ある程度の報酬単価をきちんと設定し、ストレスなくお付き合いできるお客様と、長期的に信頼関係を築いていく。それが、私の理想です。
また、新規のお客様には「こういうやり方でお願いします」といった教育コストが必ず発生します。なので、やみくもに顧問先を増やすのは、想像以上にリスクが大きいと感じています。
――なるほど。最近はどのようなお客様が増えているのでしょうか?
現在は、新規の集客は一旦ストップしているのですが、Xでのご縁から、売上数十億円規模の会社の監査役を務めさせていただいています。
その企業ではDX担当として、主担当の先生(この方もX経由で「この方こそ適任だ」と感じ、私からお声がけしてご一緒することになった先生です)とともに、バックオフィスを担うスタッフさんへの教育や、デジタル化の推進に取り組んでいます。
――DXコンサルも手がけられているのですね。
はい。クラウドストレージやマネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計の導入支援などを行っています。
スタッフさんには、まず「自分のメールアドレスを単語登録しておく」といった初歩的なところから始めていただき、メール中心だった社内のやりとりを、チャットベースに切り替えるといった改善を進めています。
動画でマニュアルを作成してナレッジベースとして蓄積するなど、属人化を防ぎつつ、誰でも確認できる環境づくりにも取り組んでいます。
DXや業務効率化に対する意欲がある企業であれば、こうした施策は確実に成果が出ると感じています。
――石野さんならではの強みというと、どのような点が挙げられますか?
一番の強みは、これまで築いてきた「人とのつながり」や「信頼のネットワーク」です。
SNSなどを通じて、さまざまな分野で活躍されている方と出会い、「誰がどんな分野に強いか」「どんな方とどんな方の相性が良さそうか」といった情報が、自然と蓄積されていきました。
私一人では対応しきれないご相談でも、スキルだけでなく”人としての相性”まで含めて、信頼できる専門家につなぐことができます。
これは単なるマッチングではなく、ご縁をつなぐ橋渡し役としての役割だと思っています。
――印象に残っているクライアントとの成功事例はありますか?
資金繰りに悩んでいた企業の経営者の方が印象に残っています。
その方は「借金=悪いこと」という固定観念が非常に強かったのですが、「まずは現金を厚くすることが大切で、利息は保険代のようなもの」という考え方を丁寧にお伝えしました。
あわせて、補助金の情報提供や融資サポートにも取り組み、最終的には資金繰りが安定し、経営にも落ち着きが生まれました。
国税時代は「税金を徴収する」という立場でしたが、今は「お客様のキャッシュをどう増やすか」という視点で寄り添える。この「向き合う方向」の違いが、独立してから一番大きく感じた変化です。

――今後の事業展開について、どのようなビジョンをお持ちでしょうか?
正直に言うと、生成AIにはワクワクする一方で、大きな脅威も感じています。「のんびりしていられないな」という危機感が常につきまとっていますね。
私自身、エンジニア出身ではありませんし、生成AIをどこまで使いこなせるかという不安もあります。ただ、国税時代には、手書き作業が本当に嫌いで、そこから逃げるようにExcel VBAやマクロを独学で習得し、独自にシステムを作り業務を効率化していました。なので、ある程度のITスキルには馴染みがあります。
それに、もともとゲームが好きなので、複数の生成AIツールを「裏技」や「コンボ」のように組み合わせて試行錯誤するのも楽しいです。とはいえ、時間はどんどん溶けていきますし、正直キリがない。
最近は特に、独学では限界を感じる場面も増えてきていて、自分のAIスキルやITリテラシーの「パラメータ」がそろそろ頭打ちだな、と。信頼して相談できるメンターがいない状態では、これ以上の成長速度や伸びしろはあまり期待できないかもしれない、という感覚もあります。
だからこそ、今は生成AIを“日常に慣らす”ことに注力しつつ、一方で「これまで培ってきた経験やコンテンツ」を改めて磨き直し、新たな武器として育てていきたいと考えています。
――その「もともと持っているコンテンツ」とは?
ひとつは、税務調査対応です。ここは、生成AIにそう簡単には代替されない領域だと感じて税務調査には、机上の知識だけでは通用しない要素が多く含まれます。たとえば、調査官の心理を読み取りながら、調査をいかに早く終わらせるかを考え、経営者の心理的ストレスや、調査対応にかかる時間的コスト・営業機会損失まで見据えたうえで、どこまで情報を開示し、調査官や統括官をどう導き、どう説得するか。その判断や現場での駆け引きには、経験に裏打ちされた「肌感覚」が不可欠です。
私は国税時代の経験があるからこそ、調査官がどんな視点で物事を見ているのか、どんな準備をしておけば調査の進行がスムーズになるのか、といった具体的かつ現実的なアドバイスが可能です。
たとえば、「税務調査では余計なことは喋るな」というのが定説ですが、「社長の熱量なら、むしろ調査官を圧倒できるので、どんどん話してください」「その姿勢が、調査官からのリスペクトや好印象につながることもあります」とお伝えすることもあります。
また、「非協力的な態度は逆効果です」といった、現場での経験に裏打ちされたリアルな知見もお伝えできる点は、自分ならではの強みだと感じています。
加えて、国税時代に「粗探しのための調査」に違和感を覚えていたこともあり、現在は「調査に来られても安心できる状態を整えておく」ことを大切にしています。顧問先から「先生に見てもらっているから安心です」と言っていただけると、当時とはまた違ったかたちで、大きなやりがいを感じます。
とくに、税務調査や相続といった分野は、専門性の高さに加え、丁寧な対話や信頼関係の構築が不可欠な領域です。AIでは代替しきれない、「人だからこそ提供できる価値」が問われる場面だからこそ、そこに自分の経験や個性を活かしていきたいと考えています。
今後は、相続分野にもさらに力を入れていくつもりです。相続は、法律・税務・感情の複雑さが絡み合う、非常に繊細で難しい領域です。だからこそ、生成AIだけでは対応しきれず、人としての関与が強く求められます。そこに自分が関わる意味と価値があると感じています。
――相続については、すでに対応されているのですか?
はい。これからさらに本格的に取り組んでいく予定です。
実際のところ、法人・個人の確定申告を含め、すべての税目に一通り対応できる体制を整えています。
なかでも税務調査への対応については、現在、共著で書籍を執筆しているところです。
――非常に幅広い対応力をお持ちなんですね。今後の組織面での展望はいかがでしょうか?
将来的には、「精鋭部隊をつくりたい」という構想があります。
私自身、税務調査対応や税務の研究、生成AIの活用など、「ワクワクできて夢中になれる領域」にもっと時間とエネルギーを注ぎたいと考えていて、そのためには、日常的な業務を信頼できるチームで支えられる体制が不可欠だと感じています。
自分が中心となって精鋭チームを立ち上げるのもひとつの選択肢ですが、すでにある優れたチームに所属税理士や社員税理士として参画させてもらう形でも構いません。
「この人の人柄と力量であれば、天邪鬼でプライドが高い自分でも素直に従える」と思える方がいれば、その傘下に入らせていただくのもアリだと考えています。
ある程度やり尽くしてきた業務については、信頼できる方に引き継ぎ、自分は自分の強みをより発揮できる領域に集中していきたい。そういった意味でも、柔軟な発想で組織のあり方を模索しています。
――かなり柔軟な発想ですね。そうしたビジョンの背景には、どのような想いがあるのでしょうか?
根っこにあるのは、「自分と関わってくれる人たちを幸せにしたい」という想いです。顧問先のお客様はもちろん、提携している士業の先生方や、身近な仲間たちも含めて、一緒に幸せになれる形を目指したいと思っています。
ただ、事務所の拡張には当然ながらリソースも必要ですし、私自身、過去に寝不足とオーバーワークで心身のバランスを崩し、入院にまで至ったことがあります。
その経験から、「無理はしすぎない」という慎重なスタンスも同時に持ち合わせています。
一方で、お客様の資産形成や資産防衛をサポートする「FP」、「プライベートバンカー」的な役割にも注力していきたいと考えています。既定の枠にとどまらず、本を執筆したり、さまざまなプロジェクトに参加したりすることで、単なる申告業務にとどまらない「価値を届けられる税理士」でありたいと考えています。
その一環として、いずれは弁護士や不動産鑑定士といった難関資格にも挑戦してみたいという気持ちもあります。
――まさに「税理士」の枠を超えた総合的な支援を目指しているのですね。
そうですね。税理士としての基礎業務はもちろん大切にしつつ、それだけでは生き残れない時代が来ていると感じています。お客様の抱える本質的な悩みや不安に向き合うには、税務だけでなく、経営や資産形成までを含めた「より広い視野」からの支援が求められていると感じます。
生成AIが発達したとしても、
といった部分は、まだまだ人間にしかできない領域だと思っています。
だからこそ、「人間にしか提供できない価値」を大切にしながら、生成AIなどのテクノロジーも積極的に取り入れて、お客様にとって本当に意味のあるサービスを届けていきたいと考えています。
――税理士を探している方や、乗り換えを検討されている方に向けて、メッセージをお願いします。
税理士選びでいちばん大切なのは、「相性」だと思っています。
これはもう、恋愛や結婚くらいの感覚で選んでいただいた方がいいかもしれません。
税理士とは、長くお付き合いしていく存在ですから、「人として合うかどうか」は本当に重要なポイントです。
また、ご自身の事業や人生のフェーズによって、求める税理士像も変わってくるはずです。たとえば、「今は1,000円カットで十分」なのか、「トップスタイリストや店長にしっかり整えてもらいたい」のか。
どちらが正解ということではなく、それぞれの状況やニーズに合った選択肢があるということです。
また、拡大志向でスピード感を求める方にとっては、ひとり税理士では対応しきれない場面も出てくると思います。というのも、急な対応や高度な専門知識が求められる状況が続くと、税理士自身の心身にリスクが生じやすくなるためです。
そういった意味では、組織的なサポート体制が整っていて、専門分野ごとに高度な人材が揃っている税理士法人のほうが、安心して任せられるケースもあるでしょう。
私はというと、「適正な料金で、店長・トップスタイリストレベルのサービスを、個別オーダーメイドで提供する」ような立ち位置を目指してやっています。
――最後に一言、お願いします。
どんな方でも、何かしらの不安や悩みを抱えていらっしゃると思います。私たちは、そうした不安を少しでも軽くできるよう、「おせっかい」と思われるくらい丁寧に寄り添ってサポートしています。
もちろん、相性は大事です。もし「この人はちょっと合わないかも」と思われたら、お互い無理をする必要はまったくありません。でも、もし少しでも「この人と話してみたいな」「相談してみようかな」と思っていただけたなら、どうぞ気軽に声をかけてください。
小さなきっかけからでも、ご縁がつながることを楽しみにしています。
石野裕之税理士事務所について