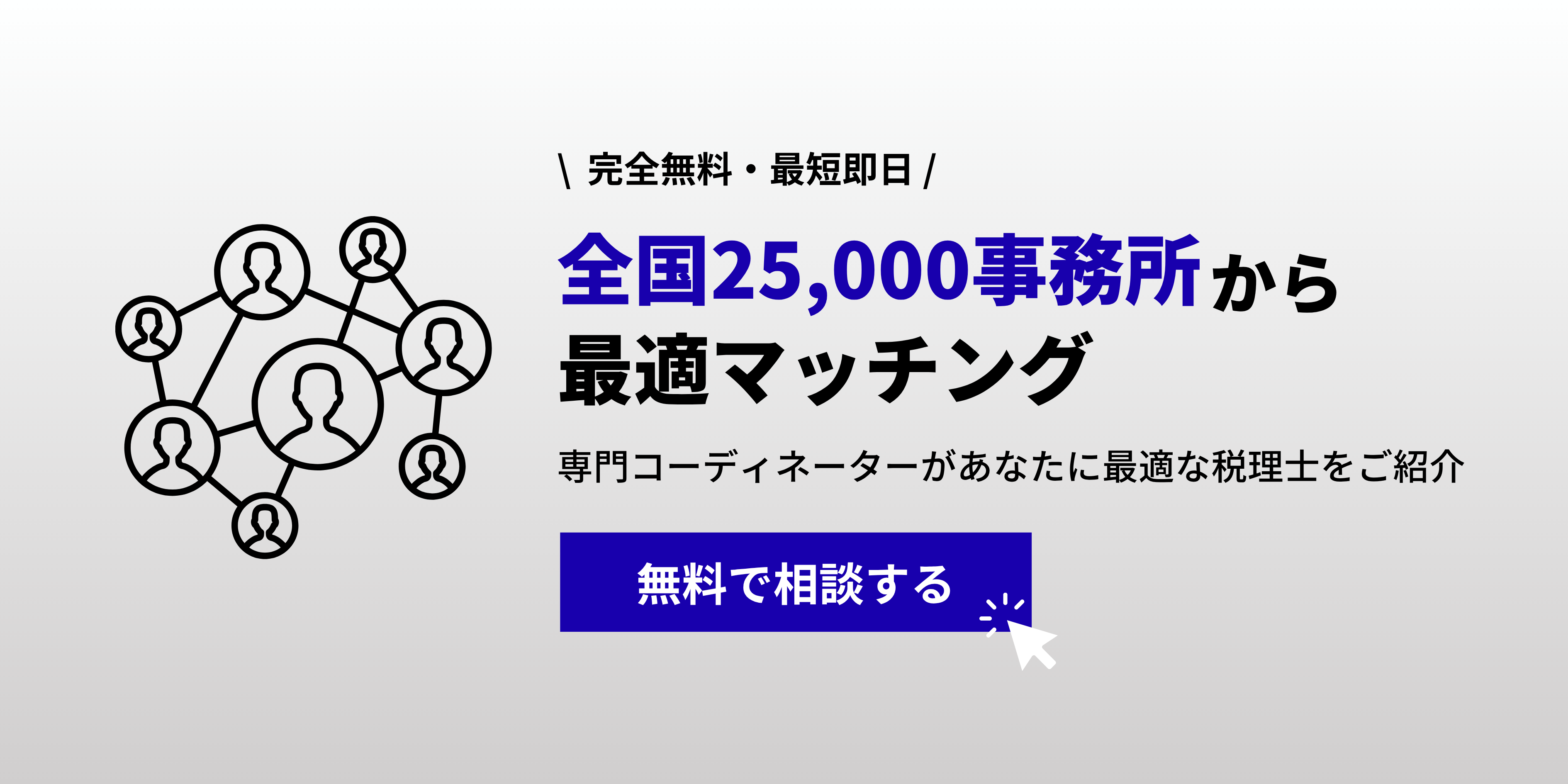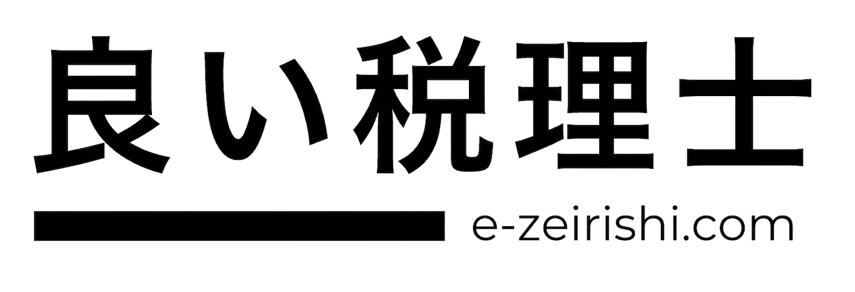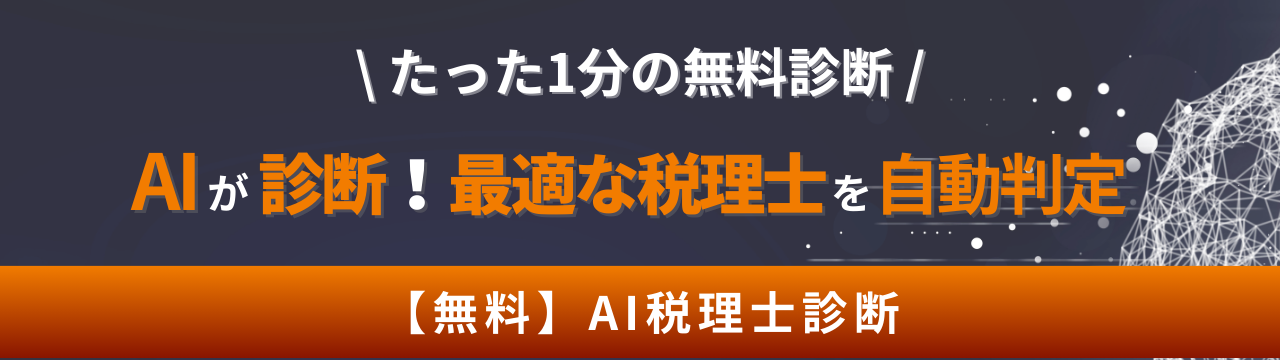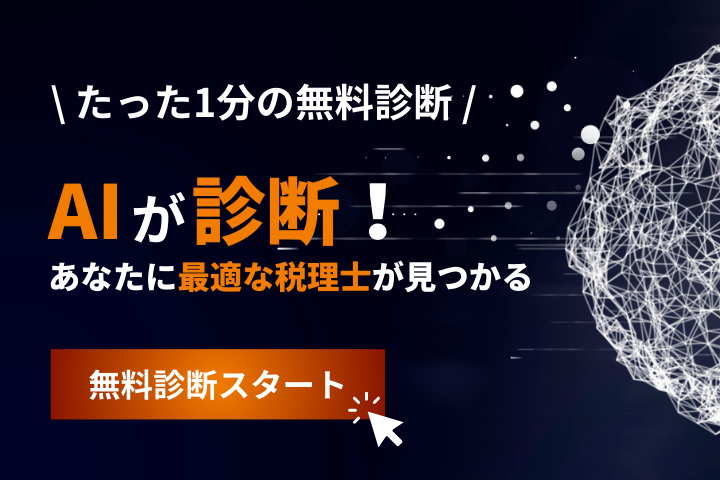不動産オーナーの“不安”を“安心”に変える、「税理士 × 大家」の挑戦

渡邊 浩滋(わたなべ こうじ):Knees bee税理士法人 代表/税理士・司法書士
大学在学中に司法書士資格を取得。一般企業での勤務を経て、実家のアパート経営を立て直した経験をもとに、2011年に開業。2018年には「大家さん専門税理士ネットワーク」を設立し、全国の家主を支援する活動を展開。
2022年にKnees bee税理士法人を設立し、代表に就任。賃貸経営に特化した税務支援を行っている。講演・執筆も多数。
インタビュアー:まずは、税理士を志されたきっかけからお聞かせいただけますか?元々はまったく異なる道を歩まれていたと伺いました。
そうなんです。最初、税理士はまったく考えていませんでした。大学では法学部に進学し、法律家を目指していました。周囲と同じように司法書士の勉強を始め、大学4年生で試験に合格できたのですが、若くして資格を取ったこともあり、このまま独立してやっていくのは少し不安がありました。もう少し社会を見て、自分にしかできない武器を見つけたい――そんな気持ちから、あえて一般企業の法務部に就職する道を選びました。
法務の仕事はやりがいもありましたが、すぐに感じたのは「税金って、何をするにもついてくる」という現実です。ところが、当時は業務が忙しすぎて、税務の勉強に時間を割く余裕がなかったんですね。そんなある日、粉飾決算を巡る裁判を担当することになりました。これが大きな転機になりました。
その裁判を通じて、初めて「会計原則」や「会計基準」といった概念に触れました。それまでは完全に文系人間だったので、会計の世界に足を踏み入れたのは初めてのことでしたが、これが驚くほど面白かったんです。
その一方で、弁護士の方が会計の話にはあまり詳しくなくて。自分の方が数字の背景や構造を理解していると気づいたとき、「これは武器になるかもしれない」と思いました。法律の知識に加えて、税務や会計の知見があれば、弁護士にも負けない領域を築けるんじゃないか。そんなふうに思い始めたのが、税理士を本格的に目指すようになった最初のきっかけです。
最初の1年は仕事を続けながら勉強を進めて、半年で国税徴収法というマイナー科目を1つ合格しました。ただ、やはり片手間では限界があって、覚悟を決めて会社を辞め、実家に戻って勉強に専念することにしました。トータルで3年半、途中からは資格の専門学校で教えながら自分も勉強する、という生活を続けました。
インタビュアー:キャリアチェンジだけでなく、学び方にも「攻めの姿勢」が感じられますね。そこまで突き動かされた背景には、どんな思いがあったのでしょうか?
実は、根底には強いコンプレックスがありました。私は中高一貫校の私立に通っていたので、大学受験を経験していないんです。なんとなくエスカレーター式に進学した結果、大学では周囲の学生がとても優秀に見えました。
その後、司法書士に合格して全国の研修に参加したときも、同世代で超優秀な人たちばかりに囲まれて、自分は本当に凡人だと思いました。神戸大学を主席で卒業した人、東北大を1年で独学合格した人など、「このまま正攻法で勝負しても敵わない」と痛感したんです。だからこそ、「自分は違う土俵で勝負するしかない」と、常に”差別化”を意識していました。
ロースクールへの進学も一時は検討しましたが、そこでもまた、競争の激しい世界に飛び込む勇気は持てなかった。じゃあ、自分は何に特化すべきか。どの分野で”戦えるか”。そう自問自答を繰り返した先に、「税理士」という選択肢が浮かび上がってきたんです。
インタビュアー:税理士としての資格取得後、いよいよ独立開業されたとのことですが、当初から”大家さん専門”に絞るという戦略は明確だったのでしょうか?
はい、かなり早い段階で「大家さん専門でいこう」と決めていました。その原点になったのは、実家の出来事です。実家はもともと不動産賃貸業を営んでおり、私が税理士の勉強で実家に戻っていた際のある日、母から「固定資産税が払えない」と相談されたんです。最初は「どうして?」という軽い気持ちで通帳や帳簿を見てみたのですが、予想以上に状況が悪くて。本当にお金が残っていなかったんです。
私は次男ということもあって、それまで家業には一切興味がありませんでした。けれどもこの件をきっかけに「大家業って、こんなにも財務が不安定になるものなんだ」と知りました。そしてさらに驚いたのが、当時ついていた顧問税理士が、その状況にまったく気づいていなかったことです。
「お金がないんです」と相談しても、「じゃあ不動産を売ったら?」というような、いかにも他人事のような返答でした。祖父母の代から受け継いできた土地を、そう簡単に手放せるわけがない。それを理解しようともせず、ただ「売ればいい」と言われたことで、「自分だったらもっと大家さんに寄り添ったアドバイスができるのに」と強く思いました。
この経験が、自分の進むべき道をはっきりさせてくれました。「自分が大家業も経験して、専門でやれば、もっと価値のある支援ができるはずだ」と確信したんです。とはいえ当時は実務経験がまったくなかったので、不動産と相続に強い税理士法人で3年ほど勤務し、現場の知見を徹底的に学びました。
その事務所は中堅規模で、所属するのは税理士ばかりという専門性の高い環境でした。やりがいも学びも多かったのですが、「いずれは独立する」という気持ちはずっと持っていましたね。
インタビュアー:実際に独立されたときは、すぐにお客さまがついたのですか?
ありがたいことに、最初から想像以上に軌道に乗りました。実は独立を見据えて、前職で働いているときから1年間かけて「新規開拓の仕込み」をしていたんです。前職の事務所が当時は比較的自由な方針で、「自分で獲得した新規案件は、将来持っていってもいいよ」と言ってくれていて。それならばと、本気で開業プランを立てました。
その一環として、自分で「大家さんの会」を立ち上げて、セミナーや勉強会などを通じて関係性を築いていったんです。そこからの依頼が独立後も継続的に入り、いわゆる”ゼロからの集客”にはまったく困りませんでした。
ただ、そこからが本当に大変でした。一人でやっていくつもりだったのに、仕事量が予想の何倍もあって、すぐに限界がきました。急遽人を採用したり、教育したりと、事業のマネジメントに追われる日々が始まりました。税務の専門家である前に、経営者としての役割が一気に増えた感覚でしたね。
現在では、私を含め税理士が2名、スタッフ全体で25名ほどの体制になっています。当初の想定とはまったく違うスケールになりましたが、それだけニーズがある分野に特化できたという意味では、非常に手応えを感じています。

インタビュアー:ここからは、大家さん向けにどのような支援をされているのか、具体的なお話を伺っていきます。まず、税務顧問というスタイルに絞っている理由を教えていただけますか?
はい。当事務所では、基本的に”顧問契約ありき”で対応しています。いわゆる「年に1回の確定申告だけお願いします」というご依頼は、現在は基本的にお断りしているんです。
もともとは私も、独立当初は確定申告だけの案件もお受けしていました。ただ、やってみてわかったのは、「このやり方では全然効率が良くない」ということでした。大家さんに特化しているからこそ、繁忙期である2月・3月に案件が集中しすぎて、業務が完全にパンクするんです。これはもう、物理的にどうにもならない。
それで、「どうすればスムーズに確定申告を乗り越えられるか」と考えた結果、定期的に情報をいただいて、日頃から数字を整えておく必要があると気づきました。今では3ヶ月に1回、定期的に資料を回収するスキームを組んでいます。この形にしてからは、お客様にとっても私たちにとっても、ずっとストレスが減りましたね。
また、顧問契約の中で法人化のアドバイスもよく行っています。たとえば、「1棟2棟買えれば満足」という方には、無理に法人化を勧めません。でも、「毎月のキャッシュフローを100万円作りたい」「将来的に10棟以上所有したい」といった明確な目標がある方であれば、法人化をおすすめします。そのほうが税務的にも、資金調達の観点からも有利だからです。
加えて、最近では融資環境が厳しくなっている影響もあり、「銀行対策」や「決算書の見せ方」といった相談が非常に増えています。10年前であれば、ある程度自己資金と実績があれば、比較的簡単に融資が出ていたのですが、今は金融機関の審査がシビアになってきています。そこで、私たちは”攻め”のアプローチを強化しているんです。
インタビュアー:”攻めのアプローチ”というのは、具体的にはどのようなことをされているのでしょうか?
ひとつは、決算書の分析や改善のサポートです。銀行が融資の際に参考にする”スコアリングシート”をもとに、弊社で独自に開発したシステムで決算内容を点数化し、「どこを改善すれば評価が上がるのか」を明確にフィードバックします。たとえば、自己資本比率が足りないとか、収益性を高める余地があるとか、かなり細かく可視化できるようになっています。
もうひとつは、「事業計画の見える化」です。将来の賃貸経営における収益予測や成長シナリオをこちらも自前のシステムで作成し、しっかりとした根拠のある金融機関へのプレゼン資料として使っていただいています。
こうしたアプローチは、お客様ご本人が”事業者”として自覚を持っていることが前提になります。なので、最初に「自分の賃貸経営を、事業として捉えているか」をしっかり確認するようにしています。
実際、「買って放っておけば自動的に儲かる」と思っている方は、正直わたしたちとは合わないです。賃貸経営を”投資”ではなく”事業”として考えられる方と一緒に、長くしっかりお付き合いしていきたい。これは開業当初からずっと変わらないスタンスです。
インタビュアー:融資や事業計画への支援など、かなり実務に踏み込んだサービスを提供されている印象ですが、ITやAIの導入にも積極的と伺いました。詳しくお聞かせいただけますか?
はい、AIやシステムの活用にはかなり力を入れています。特にここ数年は、「私自身の知見やノウハウを、どう組織として再現性を持って届けられるか」という課題に真正面から取り組んできました。というのも、独立してから事務所を拡大する中で、自分が直接対応できないケースが増え、「渡邊さんに相談したつもりだったのに」と言われてしまうことがあったからです。
そこに向き合った結果、ひとつの答えが”AIによる分身化”でした。弊所では専属のエンジニアが社内にいて、私の発想や言葉をそのままシステムに落とし込む取り組みをしています。たとえば、私が過去に発信してきたコラムやメルマガ、セミナー資料、書籍といった膨大なアウトプットを読み込ませ、大家さん向けの質問に対して”私ならこう答える”という回答が自動で返せるAIを育てています。
これはただのFAQツールではなく、まさに”渡邊の分身”として、お客様とのやりとりに活用できるレベルまで進化しています。実際に、顧問先からの質問にこのAIが回答することで、対応のスピードと品質が格段に向上しました。しかも情報は週1回のメルマガで更新・蓄積されていくので、どんどん賢くなっていくんです。
また、帳簿入力のような定型業務にもAIを取り入れていて、レシートや通帳画像を読み込むと、自動で仕訳を切ってくれるOCRアプリも自社で開発しました。その結果、入力作業に追われていたパートスタッフの業務量が減り、社員がよりお客様対応に集中できるようになりました。最近では一部スタッフに週休3日制を導入するなど、働き方の改革にもつながっています。
私自身、かつて「すべてを一人で抱え込む時期」がありました。でも今は、私の頭の中をAIに託すことで、より多くの大家さんに同じ品質のサポートを提供できるようになっています。これは単なる効率化ではなく、「困っている人にちゃんと届く仕組み」をつくるための手段なんです。

インタビュアー:事務所の規模も拡大され、システム化も進められてきた中で、組織運営における難しさや葛藤などはありましたか?
正直に言うと、すごく悩んだ時期がありました。おかげさまで事務所としては順調に成長できたのですが、それに比例して、お客様対応のほとんどをスタッフが担うようになっていったんです。けれども、そのとき一番感じたのは「自分が思い描いていた”専門性の提供”が、薄れてしまうかもしれない」という危機感でした。
私自身は税理士であり、なおかつ賃貸経営者としての経験もあるからこそ、”リアルな大家の悩み”に即したアドバイスができるという強みがあります。でも、スタッフの中には税理士ではない人もいれば、大家業を経験していない人もいる。すると、お客様から「渡邊さんに相談したつもりだったのに、違う人が出てきた」と違和感を持たれてしまうケースがどうしても出てくるんです。
それがきっかけで解約に至ってしまったこともあり、「やっぱり一人でやっていた頃のほうが良かったんじゃないか」と思ったこともあります。目が届く範囲で、小さく丁寧にやっていくべきか、それとも困っている大家さんにもっと広く届けるべきか――このジレンマは、ずっと胸の中にありました。
ただ、あるとき地方のお客様から「本当に相談できる税理士がいない」という声を聞いたんです。専門特化している税理士がほとんどいない地域も多く、情報格差や支援の空白が生まれてしまっている現実に直面しました。そのとき思ったんです。「自分が一人で抱え込んでいても、こういう人たちには届かない」と。
そこから、「じゃあ自分の知識や経験を、どうやったら他の人に伝えられるのか」を本気で考えるようになりました。その結論が、前章でもお話ししたように、”AIやシステムにノウハウを落とし込む”というアプローチです。
私は一人じゃない。でも、”渡邊の頭の中”を持った存在が社内に複数存在するようにできたら、地方の困っている方にも、今まで以上に質の高い支援ができる。スタッフにも自信を持って仕事を任せられる。そんなイメージがようやく持てるようになったんです。
だから今では、拡大すること自体にためらいはなくなりました。ただし、むやみに大きくするのではなく、”質を伴った拡大”であること。それを実現するための仕組みづくりには、これからも力を入れていくつもりです。
インタビュアー:最後に、これから税理士を探す方や、今まさに経営や賃貸経営で悩んでいる方へ、渡邊さんからのメッセージをお願いできますか?
私はいつも、「税理士は単なる計算屋ではなく、”伴走者”であるべきだ」と思っています。これは私自身が経営者であり、大家でもあるからこそ、強く感じていることです。
賃貸経営って、周りから見ると”のんびり不労所得”のように思われがちですが、実際はまったく違います。常に入退去の心配があり、修繕もあり、融資も管理も全部自分で考えなければいけない。しかも、相談できる相手がなかなかいない。気軽に「うちの経営どう思う?」なんて話せる相手って、意外と少ないんですよね。
経営者も同じだと思います。資金繰りの不安、人材の課題、将来のビジョン。どれも重くて、一人で抱え込むにはあまりに大きい。だからこそ、税理士は”正確な数字を扱う人”である以上に、”安心して悩みを話せる存在”でなければいけないと思っています。
私たちは、キャッシュフローを良くするための支援も、法人化や融資対策も、AIによる業務効率化もやっています。でも、そうした技術や制度の話は、すべて”寄り添う”という姿勢の延長線上にあると思っています。
お客様にとって「相談しやすい」「話しやすい」と思ってもらえるかどうか。その土台があって初めて、専門知識やツールが生きてくる。私は、税理士としてのスキルだけでなく、信頼される人間であることを、これからも大切にしていきたいと思っています。
困ったとき、悩んだとき、ちょっと不安になったときに、ふと思い出してもらえる。そんな存在でありたいですね。