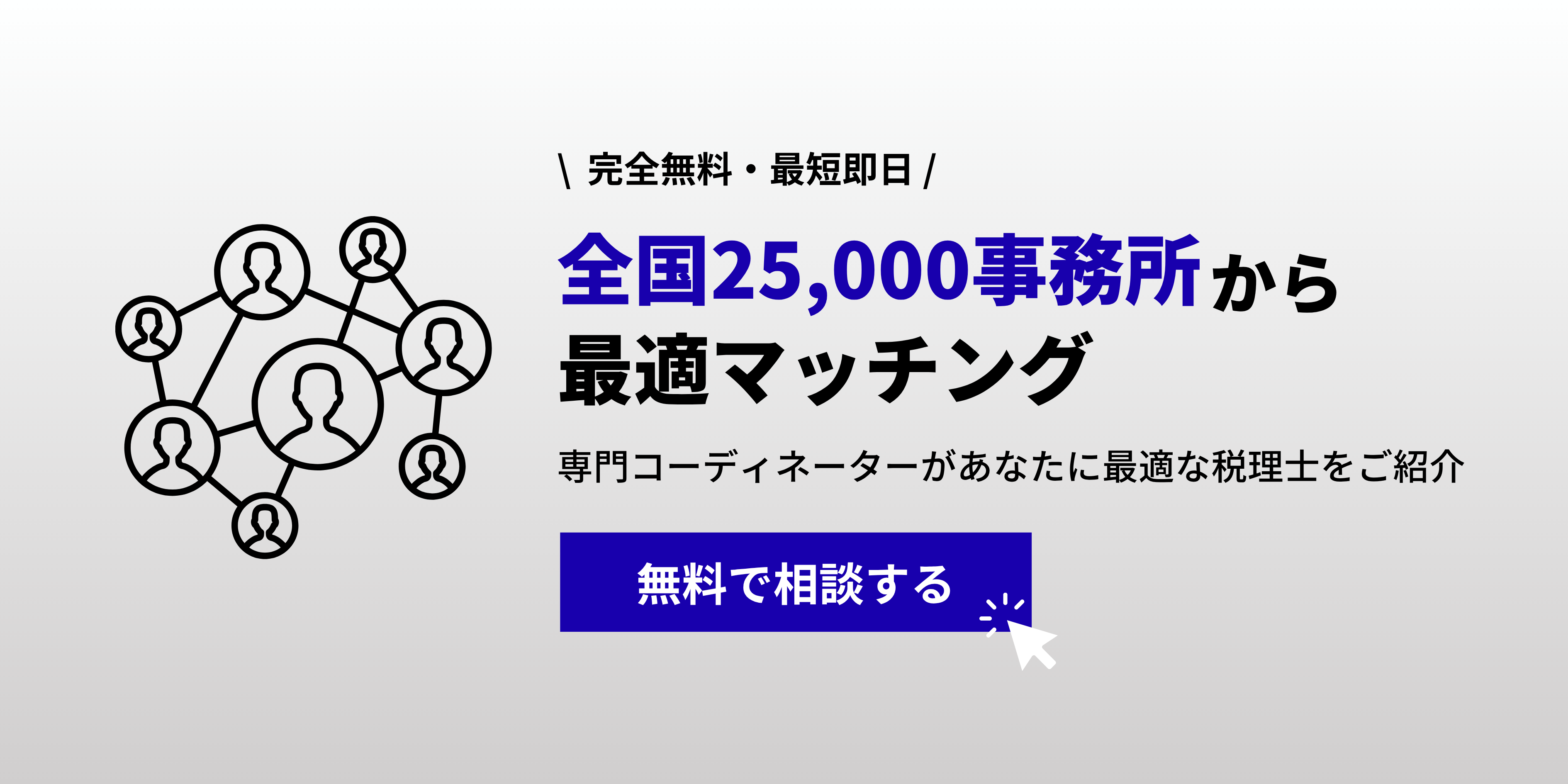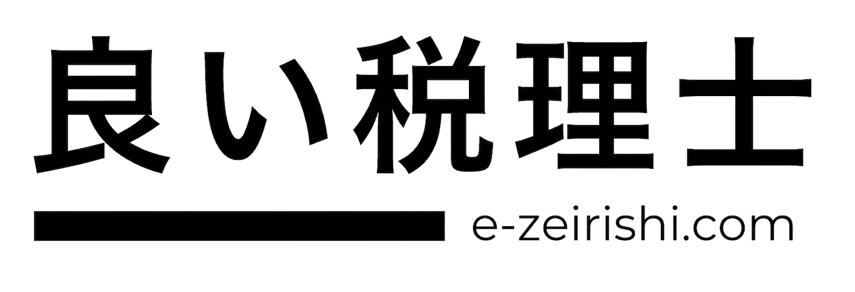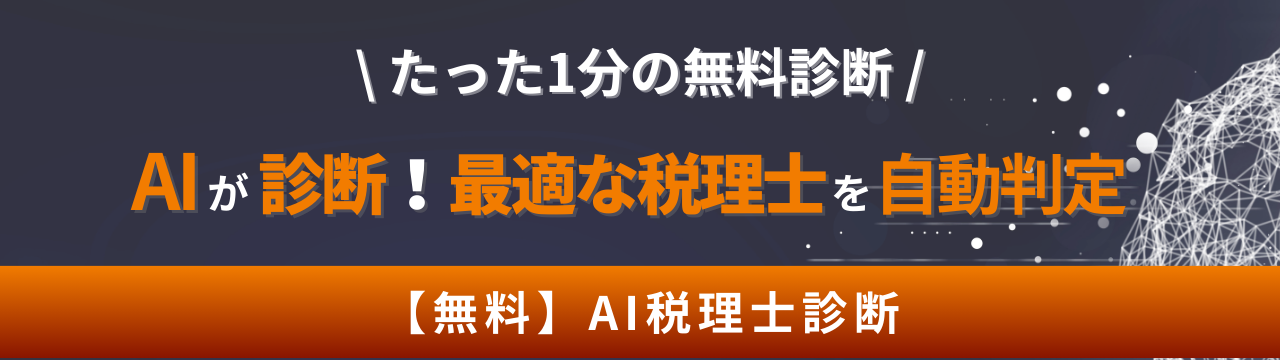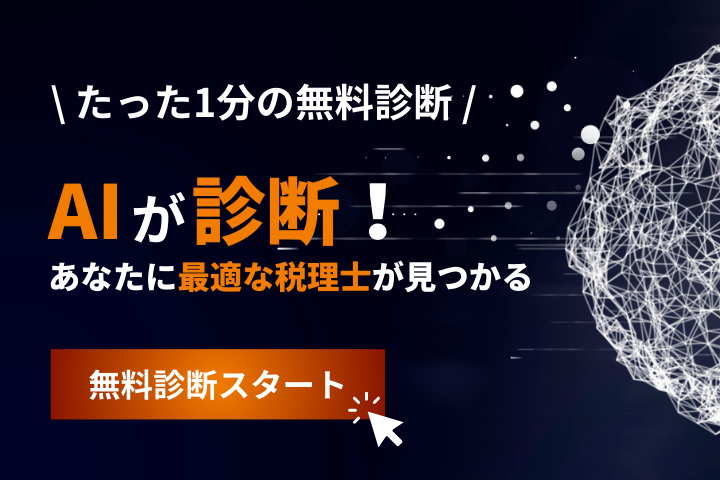北海道11万社の中小企業を支える──北海道ナンバーワンを目指す“全ての幸せの起点”とは

植島 悠介:税理士法人マッチポイント 代表税理士(写真左)
1987年生まれ。北海道新篠津村出身の農家の息子。2008年9月に島元宏忠税理士事務所(のちの税理士法人Future Create)に入社。2021年6月税理士法人Future Create代表税理士就任。2023年10月に税理士法人マッチポイントと経営統合し、代表税理士に就任。「全ての人と企業の幸せの起点となる」を理念として中小企業の伴走支援を行なっている。
鈴木 洋平:税理士法人マッチポイント CNO、マッチポイント株式会社 代表取締役(写真右)
1978年生まれ。札幌市出身。北海道大学理学部数学科卒業。道内の税理士事務所や事業会社の財務・総務部長を経験したのち、2016年に大学の同期だった小島匡彦(現・税理士法人マッチポイント共同代表)が務める税理士事務所に誘われて入社。翌年、社内ベンチャーとしてマッチポイント株式会社を設立。2019年に税理士法人マッチポイントを立ち上げ北海道で圧倒的No.1税理士事務所を目指す。
インタビュアー:早速ですが、率直にお聞きします。一般的な税理士事務所と比べて、マッチポイントさんは何が違うのでしょうか?一言で表現するとしたら?
そうですね。まず「税理士事務所に皆さんが何を期待しているか」というところに繋がると思うんですけど、やっぱり「数字に強くなってほしい」という期待があると思うんです。
たしかに。うまくいっている会社って、社長が数字に強いか、もしくは数字に強い人材がそばにいるかのどちらかですよね。
そうなんです。私たちの特徴は、決算の着地予測を全員が同じレベルで対応できる点なんです。
ホームページにも載せていますけど、「月次シミュレーション」を必ずやっていますよね。普通は決算の着地って直前にならないと見ないものなのに。
例えば、3月決算の企業があったとして、私たちは7月の段階でも「3月の着地がどうなりそうか」を確認するんです。
そうそう。うちのサービスって、基本的に2ヶ月に1回の面談じゃないですか。そのたびに必ず決算の着地を確認していますよね。
その上で、一年間の予算や目標を必ず決める。これは当たり前のようでいて、実際に徹底できている企業って意外と少ないんです。
で、それを実現するためにやっているのが「マッチポイントカレッジ」ですよね。月に1回、丸一日かけて研修をやっていて、もう6年間続けています。
だからこそ、新卒で入社して1、2年目でも高いレベルで対応できるようになるんです。
見学に来た他事務所の方が「入社2年目でこのレベルができるんですね」と驚かれることが多いですよね。
インタビュアー:なぜ決算の着地予測を重視されているのでしょうか?
うちのターゲット層は、従業員20人以下くらいの会社が多いんです。そういった会社はバックオフィスが整っていなかったり、社長があまり数字に詳しくなかったりするケースが多くて、年間の予算があいまいなまま進んでしまうんです。結果として、毎月一生懸命頑張った積み上げが、そのまま決算の数字として表れる状況になりがちなんですよね。
そうなんです。でも、やはりどの会社にも目標は必要で、追いかけていけば必ず数字は良くなっていきます。私たちはそれをシンプルに実践しているだけなんです。ただ、社長が一人でやっていくのは大変なので、そこに私たちが”壁打ち相手”として伴走するイメージですね。
実際のお客様で多いのは売上規模2億円以下の会社です。大手の税理士法人は大企業を担当するイメージを持たれるかもしれませんが、状況によって私たちはむしろ大きな会社はお断りすることもあります。
それは僕らの経営理念に直結しています。「全ての人と企業の幸せの起点となる」という理念があるからこそ、小規模な会社に特化しているんです。例えば札幌には4万3千社の中小企業があります。そのすべての会社で100万円ずつ利益が増えたら、札幌の経済は430億円活性化する。税収も増え、給与も上がり、地域全体が豊かになる。そういう未来を描いているんです。
しかも中小企業の9割には税理士がついています。だから税理士業界が「100万円の利益改善」に本気で関われば、社会を大きく変える力になると本気で思っています。
100万円の利益改善って難しそうに聞こえるけれど、例えば売上1億円の会社なら粗利を1%改善することで達成できます。だからこそ、決算着地や予算を一緒に追っていくことが大事なんです。そのプロセスの中で「この数字を改善すれば会社はよくなる」という気づきをお客様に届けたいと考えています。
現状、多くのお客様が税理士に求めているのは申告書や試算表の作成です。それだと費用は「維持管理費用」にしか見えませんし、当然安い方がいいという考えになります。
でも私たちの場合は違います。マッチポイントと関わることで会社が成長できる、成果を上げられる。そう実感してもらえるなら、税理士への支払いは「コスト」ではなく「投資」に変わるはずです。

インタビュアー:86名と税理士法人では大規模だと思いますが、かつて競合だったフューチャークリエイトさんと統合されたと伺っています。出会いはどういったきっかけだったのでしょうか?
出会いはマッチポイントが創業される約1年前の2018年8月のことです。当時お客様の相見積もり先として、鈴木さんと小島さんが当時勤めていた会計事務所さんとフューチャークリエイト(当時はシマ会計)が選ばれました。その時にお客様に選ばれたのは鈴木さんたちの勤めていた会計事務所さんでした。
どうしてフューチャークリエイトは選ばれなかったのか今後のために話を聞きたいという私の希望で、知り合いに鈴木さんと小島さんを紹介してもらい、3人が出会いました。そして意気投合したことにより交流が始まりました。
その後、前述の通り、2019年7月に税理士法人マッチポイント創業。2021年8月に税理士法人シマ会計から税理士法人フューチャークリエイトへ社名を変更し、それぞれ新たにスタートしました。
インタビュアー:お互いに若い事務所として活動される中で「手を組む」という選択をされたのはなぜでしょうか?税理士事務所同士の統合といえば、ベテランの事務所と若手の事務所の統合というパターンが多いと思うのですが。
おっしゃるとおり若手同士の統合は結構珍しい事案だったと思います。若手の事務所同士がくっつくということはあまりありません。
創業当時から会社を大きくする際に何をやらなければいけないかを考えた時に、若手同士で経営統合を主導していくということは計画の1つとして考えていました。詳しい話については こちらの記事 を見ていただきたいのですが、結論としては本気で北海道No.1を目指すなら一緒に進めたほうが良いという判断をしたからです。
インタビュアー:税理士事務所で86名という規模は、北海道では珍しいと思います。なぜここまで大きくしようと思ったのですか?
実は創業当初から「大きな事務所にしよう」とは思っていなかったんです。2019年7月の創業時に描いていたのは、50人規模で一人あたりの生産性が高く、みんなが高い給料を得られる会社でした。
でも途中で方向転換をしましたよね。その理由は、税理士業界そのものが良くなれば中小企業全体ももっと良くなると考えたからです。実際、中小企業の9割には税理士がついているというデータがありますからね。
そうなんです。もし50人規模で少数精鋭を続けたら、関われるのはせいぜい1,000社ほど。でも北海道だけでも11.5万社の法人があるので、それでは1%にも満たないんです。
しかも税理士業界の現状は小規模事務所がほとんどです。税理士法人の64%は5人未満、10人未満を含めると9割を占めている。小規模だと組織化も難しく、教育制度も整わず、結果的に「育つ人だけが育つ」という業界になってしまっています。
だからこそ、規模を追求する意味があると考えました。30人を超えると明らかに一人当たりの生産性が上がり、専門性を活かした分業が可能になってくるんです。これは規模の経済の効果ですね。
その背景にはやはり僕らの経営理念「全ての人と企業の幸せの起点となる」がありますよね。北海道で圧倒的ナンバーワンになれば知名度も上がるし、そのモデルを他の事務所にも真似してもらえる。
そうなんです。そのために僕らはノウハウをすべてオープンにしています。全国から事務所の方々が見学に来られるのも、そうした姿勢に共感いただいているからだと思います。

インタビュアー:10部門の完全分業制を徹底していると伺っています。多くの税理士事務所では「一人が最初から最後まで面倒を見る」のが当たり前です。なぜ敢えて分業制を選んだのですか?
僕らの経営理念の中には「集合天才」という考え方があります。税理士一人が最初から最後まで対応するのは、医療でいえば地域の診療所のようなもので、安心感はあるけれど専門性には限界があるんです。
そうですね。大病院では診療科が分かれているのと同じように、税理士も知らないことや不得意な分野はあります。例えば、相続を一度も経験したことがない税理士も実際に少なくないんです。
「集合天才」という発想では、基礎的なことは全員ができるのが前提ですが、その上で各自が自分の強みを伸ばしていく。そうすれば組織全体の総合力が高まり、チームとしてお客様に最適なサービスを提供できます。
例えば顧問先で相続の相談が出たとき、担当者が苦手だと避けてしまうこともあります。それではお客様のためになりません。うちでは得意なメンバーにパスできる体制があるので、担当は残しつつ「この分野はこの人が専門です」と一緒に対応できるんです。
インタビュアー:随所に理念に基づいた取り組みを感じますが、80名規模での理念徹底はなかなか難しいと思います。どのように徹底されているのですか?
僕らは「当たり前のことを徹底する」ことを大切にしています。
例えば、年1回の経営計画発表会、月1回の全体会議、週1回の全員ミーティング。こうした場を通じて、繰り返しMVVC(Mission・Vision・Value・Culture)に触れる仕組みを作っています。
創業当初から「ベンチャー税理士事務所」を掲げ、参考にしてきたのは従来の税理士事務所ではなく、世間で成長している会社です。だからこそ、理念が常に組織の中心に根付いているんです。

インタビュアー:多くの税理士は「AIに仕事を取られる」と恐れています。マッチポイントが「AIにもっと進化してほしい」と言うのはなぜですか?
最終的には、帳簿作成の部分はすべてなくなって、税額まで正確に計算してくれるぐらいまでAIに進化してほしいと思っています。現状では領収書をOCRで読み取って記帳し、試算表が作れる程度で、税額計算までは至っていません。
もし税額が自動で出せるようになれば、「税理士にしかできない仕事は何か」という本質的な問いに向き合うことになりますよね。システムで十分だというお客様はそれを使えばいい。ただ、間違ったときに誰が責任を取るのかという課題は残ります。
それでも、全ての税法を適用できるほど賢いAIが出てくるのなら、それはそれで歓迎したい。歴史を振り返れば、発明やテクノロジーの進化によってなくなった仕事はたくさんあります。
ただし、AIがどれだけ進化しても、経営に関する判断を全て社長一人が担うのは負担が大きい。だからこそ、信頼できるパートナーとしてそばにいる存在が必要なんです。
僕らはAIの進化によって、本当に価値のある仕事に集中できるようになると考えています。お客様との対話、経営相談、将来への不安を一緒に解消するといった、人間にしかできない部分にもっと時間を割けるようになる。
それは税理士にとっても、お客様にとってもプラスになります。AIを恐れるのではなく、AIがもたらす余白で「人間だからできる仕事」に注力していく。僕らが目指すのは、そういう未来です。
インタビュアー:マッチポイント不動産という関連会社を展開していますが、どういった狙いがあるのでしょうか?
売上の9割は本業ですが、その周辺でシナジーのある領域に関連事業を展開しています。その一つが不動産仲介業のマッチポイント不動産です。
相続案件を年間100件ほど扱っているので、不動産とは切っても切れない関係があります。実際、相続で一番気にされるのは「いくらで売れるか」よりも「手残りがいくらか」ですよね。
その「手残り」を正しく計算できるのは税理士だけです。不動産会社が個別の案件で「売却したら手残りはいくらです」と伝えると税理士法違反になってしまいます。特に相続では税法の特例が使えるかどうかで手残りが大きく変わるため、遺産分割の判断にも直結します。だからこそ売却までサポートするのは自然な流れなんです。
インタビュアー:他に展開予定の事業はありますか?
以前の役員会で「もし僕らが今から起業してマッチポイントに勝つとしたらどう戦うか?」という議論をしました。その結果、10月から新しいサービスを始めることにしました。
現在のサービスでは、損益計算書を図解して説明したりして、年間顧問料は大体80万円前後。記帳代行を含めると100万円を超えることになるのですが、それを支払えない層が一定数いて、いわば税理士難民になっているとも聞きます。
多くの税理士は薄利多売を避けたいので、決算申告だけを安く請け負うことを敬遠します。その結果、需要と供給にギャップが生まれているのが現状です。
しかも、規模が小さい顧問先ほど手間がかかる傾向があります。記帳が整っていなかったり、資料が揃わなかったりするためです。だから新サービスでは「返事が2週間なければ解約」「資料はこの方法で定期的に出してください」とルールを明確にし、その分料金を安くする設計にしました。
これまで税理士に期待を持てていなかった層にも、「銀行格付けではこの評価です」といったリッチな情報を提供すれば、一部はメインサービスに移行してもらえる。そんな導線を描いています。

インタビュアー:最後に、中小企業の経営者に向けて「こんな税理士事務所を選ぶべき」という基準を教えてください。
これは難しい質問ですね。というのも、多くの税理士事務所はそもそも情報発信をしていなくて、ホームページすらない事務所も珍しくありません。だから「探し方」よりも「決める基準」を考えることが大事だと思います。
そうですね。基準としては、まず「自分が税理士にやってほしいことを伝えて、それを対応できるかどうか」。そして「担当者との相性が合うかどうか」、この2つに尽きると思います。
シンプルに「税金の計算だけをしてくれれば良い」と考える経営者もいれば、「もっと会社を良くするアドバイスが欲しい」と考える経営者もいます。そのスタンスによって選ぶべき事務所は変わってきますね。
相性の部分は、私たちもすごく重視しています。マッチポイントでは担当者を決める際に「ミツカリ」という価値観診断を使っていて、顧問先にも診断をしていただきます。コミュニケーションタイプの相性を見て、より良い関係が築けるように工夫しているんです。
さらに社内研修で「エゴグラム」を全員が学んでいます。社長がどんなタイプかを理解し、「このタイプの方にはこういう言葉を選んだ方が良い」といった配慮をしながらコミュニケーションする仕組みを整えているんです。
インタビュアー:そこまで徹底されているのですね。それでは最後に一言、お願いします!
私たちは札幌に拠点を置いていますが、オンラインで全国対応しています。特に小規模の法人こそ、マッチポイントと関わることでより良い未来が開けると信じています。少しでも考え方に共感いただける方は、ぜひ一度お話しさせてください。
税理士事務所も「お客様に本当に価値を提供できているか」を常に問い直す必要があります。私たちマッチポイントもまだまだ発展途上ですが、中小企業の皆様にもっと成長していただけるよう、これからも進化を続けていきたいと思っています。
税理士法人マッチポイントについて
ご相談はこちらから

各種SNSでも情報発信中