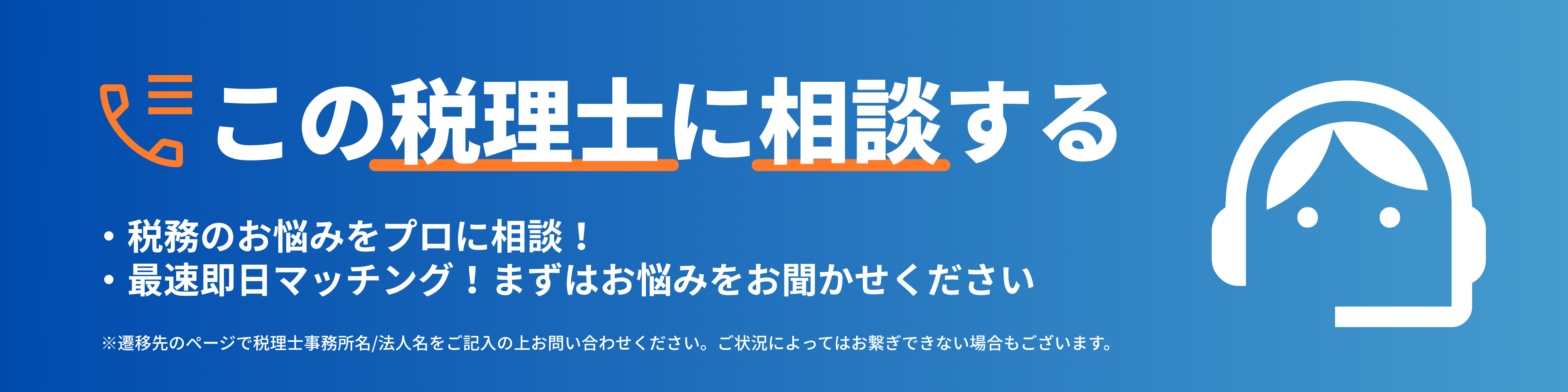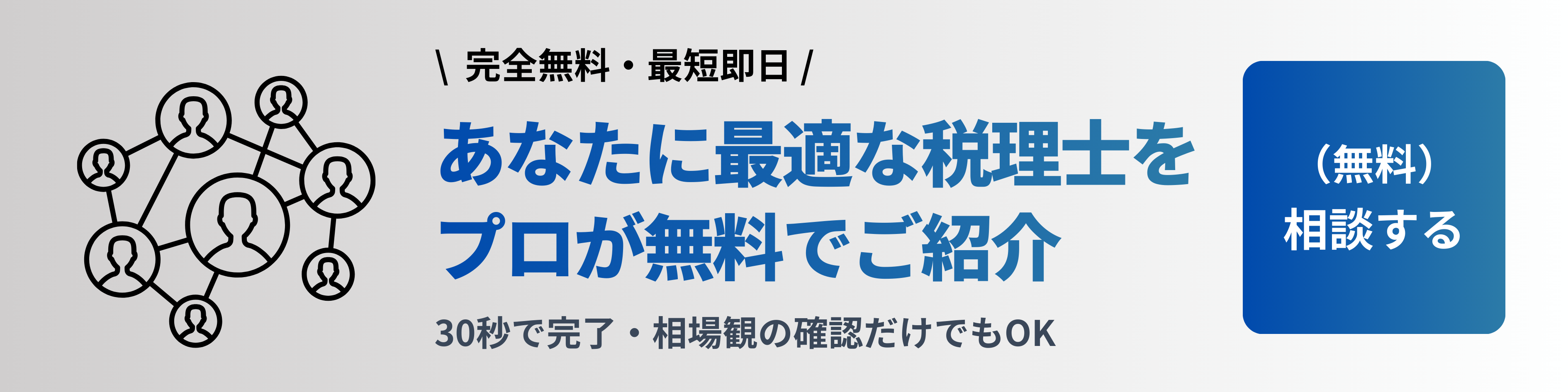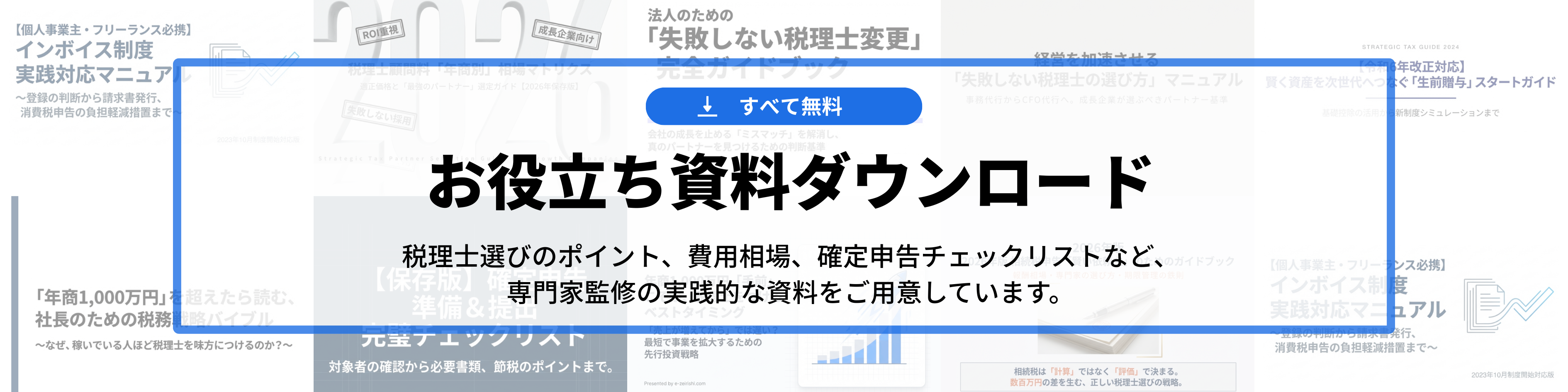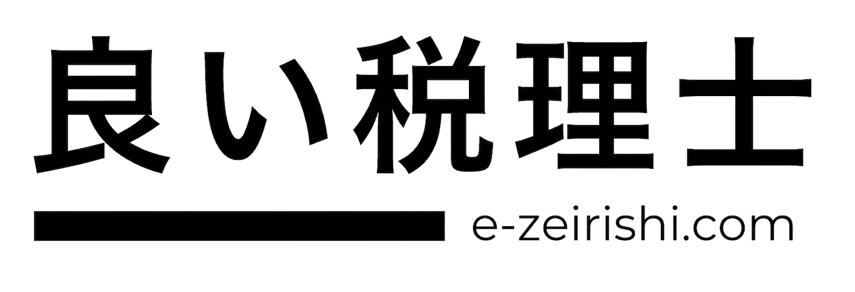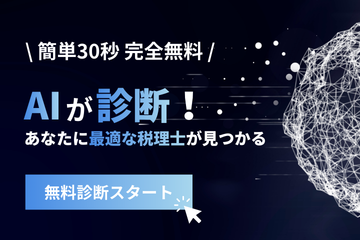『事務所にマッチしないことはやらない』さまざまな失敗が導いた『適度な変化』の事務所運営

e_zeirishi
宮﨑 雅大:宮﨑会計・税理士事務所(宮﨑雅大税理士事務所) 代表税理士
武蔵工業大学(現 東京都市大学)卒業後、一般企業や会計事務所を経て、2016年に宮﨑会計・税理士事務所(宮﨑雅大税理士事務所)を開設。開業当初から、クラウド会計の良い部分・気を付けなければならない部分を考えながら、適切な運用ができるように日々「こうすればうまくいくかな?」と模索しながら事務所を運営する。
体調不良の経験が導いた「自分らしい働き方」の発見
インタビュアー:宮﨑さんは社会人時代に2度体調を崩されたことが、税理士として独立開業するきっかけになったと伺っています。独立開業までの流れを教えていただけますか?
宮﨑氏:
はい、最初の1回目は社会人になって3ヶ月で体調を崩してしまい、退職することになりました。その当時は本当にショックでしたが、逆にそれが「この仕事を継続するより、違う道もあるのかな?」と模索するきっかけになりました。もしあの時体調を崩していなかったら、税理士にはなっていなかったと思います。大学は工学部だったので計算は苦手ではなかったですし、簿記の講義があって、お金の流れを管理することが大切なんだ!と学んでいたこともあり、退職後に簿記の資格を取りました。その流れで税理士を目指すことを決めました。
独立前はいくつかの会計事務所に勤めていました。独立したきっかけは、2回目の体調不良です。都内の会社に勤めていたのですがそこで体調を崩してしまいました。当時の職場の環境は良かったのですが、『なんでもいろいろ試したい!』と考える私とはマッチせずに、職場の皆さんに、ご迷惑をおかけしました。
そういう経験もあり「今までと違うやり方をするには独立するしかないかな?」と考えるようになりました。当時、神奈川県川崎市中原区の元住吉と武蔵小杉の間位の場所に住んでいたため、その地で独立・開業することとなりました。
はい、最初の1回目は社会人になって3ヶ月で体調を崩してしまい、退職することになりました。その当時は本当にショックでしたが、逆にそれが「この仕事を継続するより、違う道もあるのかな?」と模索するきっかけになりました。もしあの時体調を崩していなかったら、税理士にはなっていなかったと思います。大学は工学部だったので計算は苦手ではなかったですし、簿記の講義があって、お金の流れを管理することが大切なんだ!と学んでいたこともあり、退職後に簿記の資格を取りました。その流れで税理士を目指すことを決めました。
独立前はいくつかの会計事務所に勤めていました。独立したきっかけは、2回目の体調不良です。都内の会社に勤めていたのですがそこで体調を崩してしまいました。当時の職場の環境は良かったのですが、『なんでもいろいろ試したい!』と考える私とはマッチせずに、職場の皆さんに、ご迷惑をおかけしました。
そういう経験もあり「今までと違うやり方をするには独立するしかないかな?」と考えるようになりました。当時、神奈川県川崎市中原区の元住吉と武蔵小杉の間位の場所に住んでいたため、その地で独立・開業することとなりました。
インタビュアー:現在の事務所体制について教えていただけますか?
宮﨑氏:
私を含めて12名で運営しています。20代から40代まで比較的年齢層が広いです。なお、今は『拡大より充実・成長する』ことの方が、大切だと考えています。そのため事務所全体としても事務所メンバー個人としてもプラスになるような『適度なペースで成長できる環境づくり』を目指しています。
開業が2016年だったのですが、freeeやマネーフォワードが出始めた頃で、今ほど改善されたシステムではないものの、個人事業や会社の会計データを作成することができるようになって、知名度が上がり始めた時期です。体調を崩して療養中だった時期に、マネーフォワードやChatwork等のクラウド会計や最先端のツールのセミナーを調べて、「新しい仕組み」を肌で感じることができました。クラウド会計ソフトを軸にした事務所運営という着想は、この時期の経験から生まれています。
私を含めて12名で運営しています。20代から40代まで比較的年齢層が広いです。なお、今は『拡大より充実・成長する』ことの方が、大切だと考えています。そのため事務所全体としても事務所メンバー個人としてもプラスになるような『適度なペースで成長できる環境づくり』を目指しています。
開業が2016年だったのですが、freeeやマネーフォワードが出始めた頃で、今ほど改善されたシステムではないものの、個人事業や会社の会計データを作成することができるようになって、知名度が上がり始めた時期です。体調を崩して療養中だった時期に、マネーフォワードやChatwork等のクラウド会計や最先端のツールのセミナーを調べて、「新しい仕組み」を肌で感じることができました。クラウド会計ソフトを軸にした事務所運営という着想は、この時期の経験から生まれています。
「事務所にマッチしないことはやらない」断る勇気が生む強み
インタビュアー:「事務所にマッチしないことはやらない」という方針を掲げられていますが、具体的にはどのような業務をお断りしているのでしょうか?
宮﨑氏:
相続、M&A、補助金申請などの業務は行わず、税務会計と経営支援サービスに特化しています。手広く対応するのではなく、提携している中小企業診断士や社労士、公認会計士と協力して対応しています。
私の経験上、10名ぐらいの規模ですと、専門領域を広げすぎると浅く広くなってしまい、対応しきれなくなってしまうのではないかと考えています。たとえば相続専門の担当者を置けば、その分本来業務の時間が削られますし、せっかくのクラウド会計という強みも薄れてしまうのでは?と考えています。
明確な判断基準はありませんが、M&Aを目指すような大規模案件や医療法人など、対応できるメンバーが限られる分野に関しては今は受けないほうが良いかなと感じています。ですので、専門外の内容だったり、この内容だと他の士業の方をおつなぎしたほうが良いのでは?と感じた時は提携先にお繋ぎしています。
顧問先はfreeeやマネーフォワード等のツールに抵抗がないような、感覚の若い方が比較的多いですね。世代や業種に関係なく、新しいツールへの適応力がある方という意味です。また地域は神奈川県の川崎市・横浜市を中心に、東京23区・多摩地区が中心ですが、オンラインで完結するお仕事内容でしたら、北海道から沖縄まで全国に対応しています。
相続、M&A、補助金申請などの業務は行わず、税務会計と経営支援サービスに特化しています。手広く対応するのではなく、提携している中小企業診断士や社労士、公認会計士と協力して対応しています。
私の経験上、10名ぐらいの規模ですと、専門領域を広げすぎると浅く広くなってしまい、対応しきれなくなってしまうのではないかと考えています。たとえば相続専門の担当者を置けば、その分本来業務の時間が削られますし、せっかくのクラウド会計という強みも薄れてしまうのでは?と考えています。
明確な判断基準はありませんが、M&Aを目指すような大規模案件や医療法人など、対応できるメンバーが限られる分野に関しては今は受けないほうが良いかなと感じています。ですので、専門外の内容だったり、この内容だと他の士業の方をおつなぎしたほうが良いのでは?と感じた時は提携先にお繋ぎしています。
顧問先はfreeeやマネーフォワード等のツールに抵抗がないような、感覚の若い方が比較的多いですね。世代や業種に関係なく、新しいツールへの適応力がある方という意味です。また地域は神奈川県の川崎市・横浜市を中心に、東京23区・多摩地区が中心ですが、オンラインで完結するお仕事内容でしたら、北海道から沖縄まで全国に対応しています。

自律的に動くチーム制組織の秘密
インタビュアー:『お勉強会チーム』など、メンバーの方からも積極的な情報発信があると伺っています。社内では現在どのような取り組みがなされているのでしょうか?
宮﨑氏:
完全なボトムアップではありません。メンバーの特性に合わせて役割分担を行い、現在はチーム制で運営しています。
最近、組織編成を変えました。「機動的に動く4名のチーム」と「通常チーム」8名(AとBに分かれる)で構成されています。機動的に動くチームは私と他の税理士が中心となり、新規顧客や難しい案件、通常チームの相談役を担当。通常チームが日常的な税務会計業務を担当します。
このチーム制は、4~5年前から導入しているのですが、事務所メンバーのスキルやキャラクターに合わせて、変更しています。今回、新しいチームに編成し直しているのも、その一環です。
上記以外にグループの枠を越えた『委員会活動』も、勉強会、情報発信、データ整理(ファイル・フォルダ構造の最適化)、運営管理(労務管理・ルール作り)があります。私が考える答えより良い提案があれば採用しますし、うまくいかなければ従来の方法に戻ることもあります。
完全なボトムアップではありません。メンバーの特性に合わせて役割分担を行い、現在はチーム制で運営しています。
最近、組織編成を変えました。「機動的に動く4名のチーム」と「通常チーム」8名(AとBに分かれる)で構成されています。機動的に動くチームは私と他の税理士が中心となり、新規顧客や難しい案件、通常チームの相談役を担当。通常チームが日常的な税務会計業務を担当します。
このチーム制は、4~5年前から導入しているのですが、事務所メンバーのスキルやキャラクターに合わせて、変更しています。今回、新しいチームに編成し直しているのも、その一環です。
上記以外にグループの枠を越えた『委員会活動』も、勉強会、情報発信、データ整理(ファイル・フォルダ構造の最適化)、運営管理(労務管理・ルール作り)があります。私が考える答えより良い提案があれば採用しますし、うまくいかなければ従来の方法に戻ることもあります。
インタビュアー:このような文化はどうして形成できたとお考えですか?
宮﨑氏:
正直、メンバーに助けられているというのが実感です。私自身、試行錯誤で完璧とは言えない運営をしてきましたが、メンバーが我慢と理解をしてくれて現在の取り組みができていると考えています。
私たちの事務所は「なんでも最先端なことに取り組んでいる」わけでもなく、「新しいことに全く取り組まない」というわけでもありません。『私達の事務所の風土や文化にマッチしそうなことを取り入れながら、適度なペースで変化し続ける』という、中途半端な立ち位置だと考えています。良いと思ったら変化し、今ではないと感じたら見送る。例えば税理士界隈ではAI導入が盛んに叫ばれていますが、私達の事務所では流行りに乗って無理に業務を変えるのではなく、自然な形で取り入れています。
多様性を求めすぎず、税務会計という土台をしっかり固めることで、freeeやマネーフォワードを使った自計化、記帳代行、半自計化といったサポートが提供できています。
正直、メンバーに助けられているというのが実感です。私自身、試行錯誤で完璧とは言えない運営をしてきましたが、メンバーが我慢と理解をしてくれて現在の取り組みができていると考えています。
私たちの事務所は「なんでも最先端なことに取り組んでいる」わけでもなく、「新しいことに全く取り組まない」というわけでもありません。『私達の事務所の風土や文化にマッチしそうなことを取り入れながら、適度なペースで変化し続ける』という、中途半端な立ち位置だと考えています。良いと思ったら変化し、今ではないと感じたら見送る。例えば税理士界隈ではAI導入が盛んに叫ばれていますが、私達の事務所では流行りに乗って無理に業務を変えるのではなく、自然な形で取り入れています。
多様性を求めすぎず、税務会計という土台をしっかり固めることで、freeeやマネーフォワードを使った自計化、記帳代行、半自計化といったサポートが提供できています。
クラウド会計の黎明期から取り組んできた経験が生む「ちょっとした工夫」の価値
インタビュアー:クラウド会計を当初から使われていますが、業務や価値提供に変化はありましたか?
宮﨑氏:
開業当初から使用しているため、価値提供自体に大きな変化はありません。しかし、長年の経験から「ちょっとした工夫で作業を楽にする」提案ができるようになってきたと感じています。
大規模なシステム導入ではなく、現状を少し改善する”ちょっとした”提案です。例えば、クラウド会計を使っても入力の段階が整理されていなければ意味がないため、そのような場合は正直にお伝えします。何でもお客様の言いなりになるのではなく、結果として『今までの方法を変更しませんか?』という提案をすることとなります。
顧問業務では記帳代行から決算申告まで幅広く対応していますが、完全自計化を強制することはありません。自計化が難しい場合は記帳代行への切り替えも可能で、途中での変更にも柔軟に対応しています。多くの事務所で自計化がうまくいかないケースを見てきたため、このような柔軟性を重視しています。
お客様の期待値も開業当時と比べると変わってきていると考えています。最初は『価格重視』でクラウド会計を利用される方が多かった印象ですが、次第に「業務効率化」などを希望されてクラウド会計を導入検討される方が増えてきた印象です。結果として、資金繰りなどの相談を受ける機会も増えています。
開業当初から使用しているため、価値提供自体に大きな変化はありません。しかし、長年の経験から「ちょっとした工夫で作業を楽にする」提案ができるようになってきたと感じています。
大規模なシステム導入ではなく、現状を少し改善する”ちょっとした”提案です。例えば、クラウド会計を使っても入力の段階が整理されていなければ意味がないため、そのような場合は正直にお伝えします。何でもお客様の言いなりになるのではなく、結果として『今までの方法を変更しませんか?』という提案をすることとなります。
顧問業務では記帳代行から決算申告まで幅広く対応していますが、完全自計化を強制することはありません。自計化が難しい場合は記帳代行への切り替えも可能で、途中での変更にも柔軟に対応しています。多くの事務所で自計化がうまくいかないケースを見てきたため、このような柔軟性を重視しています。
お客様の期待値も開業当時と比べると変わってきていると考えています。最初は『価格重視』でクラウド会計を利用される方が多かった印象ですが、次第に「業務効率化」などを希望されてクラウド会計を導入検討される方が増えてきた印象です。結果として、資金繰りなどの相談を受ける機会も増えています。
AI時代に求められる税理士の「人間臭さ」とは
インタビュアー:AI時代における税理士の価値について、どのようにお考えでしょうか?
宮﨑氏:
AIが事前準備や作業を担当する時代が来るのでは?と予想しています。そういう時代になったらますます、人間は判断業務と「人間臭さ」が重要になり、フロントでの判断やAIからの回答の正誤判断は人間が行ったほうが良いと考えています。
この認識から、事務所の勉強会も経営支援ツールの使い方から税務会計の基礎に変更しました。メンバーから「税務会計を極めたい」という声が上がったためです。土台となる税務会計の知識こそが、AI時代に求められるスキルやキャラクターなのでは?と感じています。
そして、相手を全否定せず、相手に一方的に合わせてもらうのでもない「人間臭い」関係性も大事になると考えています。税理士と顧客は共同作業であり、お互いを理解し合って進めることが重要です。手取り足取りのサポートを期待される方とは、事務所のスタイルが合わない可能性があります。
今後10年で作業領域はAIが担うようになり、人間は確認や工夫の領域が増えると予想しています。システムの一律導入ではなく、お客様の状況に応じた判断がより重要になるでしょう。ITに詳しくない方にAI前提のシステムを導入すると、ブラックボックス化して対応できなくなるリスクもあると考えています。
メンバーには、新しいツールを導入した際にも税務会計の基礎をしっかり固めてほしいと考えています。環境変化に適度に対応できる柔軟性も重要になってくるのでは、と予想しています。
AIが事前準備や作業を担当する時代が来るのでは?と予想しています。そういう時代になったらますます、人間は判断業務と「人間臭さ」が重要になり、フロントでの判断やAIからの回答の正誤判断は人間が行ったほうが良いと考えています。
この認識から、事務所の勉強会も経営支援ツールの使い方から税務会計の基礎に変更しました。メンバーから「税務会計を極めたい」という声が上がったためです。土台となる税務会計の知識こそが、AI時代に求められるスキルやキャラクターなのでは?と感じています。
そして、相手を全否定せず、相手に一方的に合わせてもらうのでもない「人間臭い」関係性も大事になると考えています。税理士と顧客は共同作業であり、お互いを理解し合って進めることが重要です。手取り足取りのサポートを期待される方とは、事務所のスタイルが合わない可能性があります。
今後10年で作業領域はAIが担うようになり、人間は確認や工夫の領域が増えると予想しています。システムの一律導入ではなく、お客様の状況に応じた判断がより重要になるでしょう。ITに詳しくない方にAI前提のシステムを導入すると、ブラックボックス化して対応できなくなるリスクもあると考えています。
メンバーには、新しいツールを導入した際にも税務会計の基礎をしっかり固めてほしいと考えています。環境変化に適度に対応できる柔軟性も重要になってくるのでは、と予想しています。
経営者として伝えたい、税理士との理想的な付き合い方
インタビュアー:同じ経営者として、税理士との付き合い方についてメッセージをお願いします。
宮﨑氏:
理想的なのは「税理士や会計事務所の職員の方々と一緒にルールを作る事」だと考えています。任せきりではなく、足並みを揃えて対応する。税理士から「ここは作業的に難しい」と言われた時は協力し、無理に押し付けない。そのようなスタンスでルール作りをするのが良いのでは?私は考えています。
一方で、まったく疑問を持たず成長しない経営者も問題です。作業だけに集中して、確認や説明の時間を取らない方もいらっしゃいますが、それでは本来の価値を得られません。税理士や会計事務所の職員の方々と一緒にルールを作り、お互いに理解し合いながら進める。そんな共同作業の感覚が大切ではないでしょうか。
理想的なのは「税理士や会計事務所の職員の方々と一緒にルールを作る事」だと考えています。任せきりではなく、足並みを揃えて対応する。税理士から「ここは作業的に難しい」と言われた時は協力し、無理に押し付けない。そのようなスタンスでルール作りをするのが良いのでは?私は考えています。
一方で、まったく疑問を持たず成長しない経営者も問題です。作業だけに集中して、確認や説明の時間を取らない方もいらっしゃいますが、それでは本来の価値を得られません。税理士や会計事務所の職員の方々と一緒にルールを作り、お互いに理解し合いながら進める。そんな共同作業の感覚が大切ではないでしょうか。
インタビュアー:改めて、宮﨑会計・税理士事務所の強みを教えてください。
宮﨑氏:
一言で表すなら、「私たちのペースで変化する」ことです。革新的でも現状維持でもない。「今」と「ちょっと先」と「将来・未来」を見据えながら、適度な変化を続ける事務所です。これが合っていると感じた時に変化し、そうでなければ見送る。この柔軟性が私たちの特徴だと思います。
当事務所の経営理念は、『「今」と「ちょっと先」と「将来・未来」を見据えて、お客様も、スタッフ同士も、安心を提供できる事務所を目指す』です。少し長いのですが、一字一句に大切な思いを込めています。
「今」だけではなく、「ちょっと先」や「将来・未来」という複数の時間軸を含めているのは、複眼的思考で物事を捉える姿勢が大切だと思うからです。今はこの方法がよいけれど、来年はこれを試してみましょう、というように柔軟に考えることで、変化やチャレンジを前向きに捉えられるのでは?と考えています。
そして、お客様にもメンバーにも「安心を提供できる事務所」であることを常に意識しています。私たちがお客様に安心を提供するのはもちろん、お客様からも安心を提供してもらえるような関係でありたい。そんな相互理解の関係性を大切にしています。
紆余曲折ありながら始まった税理士人生でしたが、それが現在の事務所運営につながっていると考えています。断る勇気、メンバーの自主性、そして「ちょっとした工夫」の積み重ね。AI時代においても人間らしい価値を提供し続けることで、税理士と経営者が共に成長する関係を築いていけるように、失敗をしながら日々精進しているのでは?と考えています。
完璧を求めるのではなく、お互いを理解し合いながら適度な変化を続ける。そんな姿勢が、これからの時代に求められているのではないでしょうか。もし私たちのような考え方に共感いただけるようでしたら、ぜひ気軽にご相談ください。一緒に、「今」だけはなく、「ちょっと先」や「将来・未来」のために最適な方法を見つけていきましょう。
一言で表すなら、「私たちのペースで変化する」ことです。革新的でも現状維持でもない。「今」と「ちょっと先」と「将来・未来」を見据えながら、適度な変化を続ける事務所です。これが合っていると感じた時に変化し、そうでなければ見送る。この柔軟性が私たちの特徴だと思います。
当事務所の経営理念は、『「今」と「ちょっと先」と「将来・未来」を見据えて、お客様も、スタッフ同士も、安心を提供できる事務所を目指す』です。少し長いのですが、一字一句に大切な思いを込めています。
「今」だけではなく、「ちょっと先」や「将来・未来」という複数の時間軸を含めているのは、複眼的思考で物事を捉える姿勢が大切だと思うからです。今はこの方法がよいけれど、来年はこれを試してみましょう、というように柔軟に考えることで、変化やチャレンジを前向きに捉えられるのでは?と考えています。
そして、お客様にもメンバーにも「安心を提供できる事務所」であることを常に意識しています。私たちがお客様に安心を提供するのはもちろん、お客様からも安心を提供してもらえるような関係でありたい。そんな相互理解の関係性を大切にしています。
紆余曲折ありながら始まった税理士人生でしたが、それが現在の事務所運営につながっていると考えています。断る勇気、メンバーの自主性、そして「ちょっとした工夫」の積み重ね。AI時代においても人間らしい価値を提供し続けることで、税理士と経営者が共に成長する関係を築いていけるように、失敗をしながら日々精進しているのでは?と考えています。
完璧を求めるのではなく、お互いを理解し合いながら適度な変化を続ける。そんな姿勢が、これからの時代に求められているのではないでしょうか。もし私たちのような考え方に共感いただけるようでしたら、ぜひ気軽にご相談ください。一緒に、「今」だけはなく、「ちょっと先」や「将来・未来」のために最適な方法を見つけていきましょう。
📣 宮﨑会計・税理士事務所 の情報はこちら